2019/02/06
イヤホンをしているあなたは、もうサイボーグなのかも知れない(後編)
DENTSU LIVE | 電通ライブ
小川:きょうは銀座でボーカロイドオペラ『THE END』の話ができるというので、ぼく自身、ちょっと興奮しています(笑)。『THE END』は、ご存じのとおり、音楽家の渋谷慶一郎さんが中心となって、サウンドアーティストのevalaさんやアーティストのYKBXさんらとコラボしてつくったメディアアート作品で、主演はボーカロイドの初音ミク。オーケストラはもちろん歌手も含めて、人間が出てこない世界初のオペラです。初演は、阿部さんがいらしたYCAM(山口情報芸術センター)でしたね。
阿部:そうです。YCAMは劇場的なものも含めてさまざまなメディアアート作品をプロデュースしていますが、『THE END』は、その一つとして、2012年にぼくがプロデュースしました。
小川:実はぼくもそのときのオーディエンスの一人だったので、初演のすごさも知っているのですが、さらにすごいなと思うのはその後です。翌年には、東京のBunkamuraとパリのシャトレ座で公演していますよね。その後もオファーが絶えなくて、初演から5年近くになるいまでも、世界のあちこちを巡回しています。

渋谷:去年はアブダビでもやりましたね、UAEの。その前はデンマークのオーフスとドイツのハンブルク、それにオランダのアムステルダムです。
阿部:ともするとすぐに過去のものになりがちなメディアアート作品が、5年たっても古くなるどころか、いまだに現在進行形なんですよね。リアルタイムの表現として、これだけ継続して世界中で受け入れられているのは、すごく珍しいことですよ。
小川:始まりは、阿部さんから渋谷さんへのオファーでしたよね?
渋谷:そうです。『THE END』に関しては、2012年に阿部さんから「何か新しい作品をつくりませんか」と声を掛けていただいたのが始まりでした。YCAMでは、その前にもサウンドインスタレーションをいくつかやってはいますが。
阿部:最初は『filmachine』でしたね。あれもヨーロッパで評価が高かった。

渋谷:ぼく自身も、画期的な仕事だったと思っています。いまでこそサラウンドやマルチチャンネルがはやりみたいになっていて、いろんなアーティストが使っているけれど、当時はまだ誰もやっていませんでしたから。あのころ、ぼくは複雑系の理論でつくったノイズを再生したいと思っていたのだけど、ふつうのスピーカーだと情報量が多すぎて、単なるノイズにしか聞こえなかったんです。でも、データ自体にはある種の規則性や周期性があるわけで、そういうものを伝えるのにどういう方法があるのかなと考えたときに、たどり着いたのがサラウンドだった。それをevalaくんと一緒にやったのが『filmachine』でした。
阿部:少し補足すると、サラウンドというのは、立体音響のことです。アートの夢は、映像にしても、音にしても、立体なんですよ。それを音でトライしたという点で、『filmachine』は世界的なはしりだったんです。
渋谷:例えば、新幹線が目の前を通り過ぎていくときには、すごい体感があるじゃないですか。その体験自体をぼくらは音でつくるんです。それどころか、新幹線だとできない、音が身体を突き抜けていくような超自然的な体験をつくったりもできます。
evala:サラウンドというのは、いかに臨場感があるかということですからね。そういう意味では、新しい自然現象を人工的につくっているのに近いかもしれません。
渋谷:そういったことを『filmachine』でやりながら、自分たちのサウンドインスタレーションは、体験自体をデザインするという意味では現代のオペラだな、と思ったんです。ぼくのなかでは、そのあたりからオペラが引っかかっていましたね。もちろんワグナーがやっていたようなものではなく、まったく新しい体験としてのオペラですが……。実際に、そういうものをやりたいとは当時もevalaくんと話していて、いろんなことをやり始めてもいた。阿部さんからオファーをもらったのは、ちょうどそんなときだったんです。
だから、何をやりたいのかと聞かれて、すぐにオペラと答えたのだけど、その時点でのアイデアは、自分のなかにあるオペラのイメージとevalaくんのサラウンドを組み合わせることでした。でも、そうこうするうちに、偶然、横部くん(YKBX)と知り合って……。彼はすごい、と率直に思いましたね。ぼくはアニメ好きでもないし、オタクでもないのだけど、作品の情報密度が自分と合うというか。すぐに一緒にやろうという話になって、そこからアニメーションの比重がどんどん増えていったんです。
小川:初音ミクを使うことは、どうやって決まったのですか?

渋谷:『THE END』のベースには、妻を亡くしたというぼく自身の個人的なテーマがあって、ストーリーのなかにも亡霊の声が歌うという設定が出てきます。それを誰が歌うのかと考えたときに、初音ミクがいいんじゃないかという話になった。そこからさらに話が進んで、出てくるのは初音ミクだけにしたほうが面白いんじゃないか、ということで落ち着きました。
阿部:オペラは1600年ごろにヨーロッパでできたのですが、宗教的なものは別として、当時は人間の声で何かを表現する初めての試みでした。だから、人間が出てこないオペラというのは、それだけでもすごいことなんです。
さらに、『THE END』は音響も映像も衝撃的です。例えば、先ほどアートの夢は立体だと話しましたが、ホログラムを使えば、立体映像はつくれます。ただ、いまの技術だと小さなものしかできない。せいぜい人間の等身大くらいのものです。そういう制約を超えて、2000人規模のホールでなんとか立体映像を見せようと、さまざまな工夫をしてもいますよね。
YKBX:難解な脚本のなかで、ビジュアルでどこまで説得力を出せるかという部分では、かなり試行錯誤を重ねましたね。複数のスクリーンを使って、プロジェクションマッピングをしたりしながら、2次元の見え方ではなくて、複雑な見え方になるように設計して…。劇場によってステージの形も客席からの見え方も変わりますから、それに応じてセッティングを細かく調整したりもしています。

阿部:加えて、もちろん音の面でも、人間の脳のなかに立体が浮かぶような挑戦をしています。YCAMでやったときも、相当な数のスピーカーを使いましたよね。
evala:YCAMに限らず、劇場そのものを音響体にするイメージでつくり込んでいるので型通りにはスピーカーの数も決まらず、いつもびっくりするほど多くなりがちです。全てのウーファーを客席の下に仕込んだりもしました。
小川:そうやってつくられたものを実際に体験してみると、まず序曲でやられます(笑)。弦の音がすごくナチュラルに聞こえてくるんだけど、それが絶対に現実ではあり得ないような空間の飛び回り方をしますから。
evala:オーディエンスがびっくりしているのは、後ろから見ていても分かりますね。例えばシャトレ座は4階建てですが、その空間を音が上下に動き回るなんて、誰も体験したことがないわけですし。
でも、オペラハウスや劇場って、そもそもステージの音がホール内にきれいに行きわたるような設計がなされているので、立体音響をやるには、本当はすごく不適切な場所なんです。だから、音の調整はかなり徹底してやらなくてはいけないのですが……。

小川:最近はテクノロジーを駆使すれば、極端なことをいえば、家にいてもコンサート会場にいても同じ体験ができると思われがちだけど、本当はそうじゃないということですね。やっぱり、その場に行かないと体験できないことがある。
渋谷:特に音はそういうものなんでしょうね。あとは必然性、かな。ときどき映像作品を大きく映しているだけの美術展があるのですが、ほとんどはあま面白くないんです。大きく見せても構わないのだけど、それ自体にどのくらいの意味や必然性があるのか。そこがきちんと成立している作品って、意外と少ないと思うんですよ。音も同じで、劇場や美術館でやるのなら、そこでしかできないことをやらないと意味がない。
小川:2015年のオランダのアムステルダム以降、ぼくは海外公演のプロデューサーとして一緒にツアーをまわらせてもらっているわけですが、そばでevalaさんのお仕事を見ていると、すごくデジタルな部分の仕事と、現場で体験をつくっていくような手作業に近いような仕事との両方がありますよね。F1なんかでも、それぞれのサーキットに合わせて、マシンについてのベストなセッティングをつくっていきますが、あれに近いつくり込みを、その都度やるじゃないですか。
evala:サラウンドの音響のチューニングは、オリジナルとしてあるものをただ生々しくリアルに再現するのとは違いますからね。ぼくらがつくっている体験は、いわば“空間のいたずら”で、ダイレクトに感覚に訴えかけてきます。それをぼくは「耳で視る」と言ったりしているのですが、つくるときにもやっぱり「耳で視る」んです。目に見えないものにフォーカスしながら、手間をかけて、その都度つくり込んでいくしかない。
小川:そうやって、そこでしか体験できないものをつくっていくからこそ、あの作品には今日性があるのでしょうね。
阿部:それはそうかもしれません。メディアアートの世界でいうと、60年代の後半くらいに、ジェームズ・タレルなんかも非常にパーソナルな体験づくりに取り組んではいたんです。でも、精度がずっと粗かった。それを最高に緻密な精度でやっているのがevalaさんです。そういう意味では王道なのだけど、結局、メディアアートの面白さというのは個人の体験にどうアクセスするかということなんですよ。『THE END』は、そこを非常に納得性の高いレベルで実現できているからこそ、いまなお古くなることなく、注目されつづけているのだと思いますね。

音楽家
1973年生まれ。東京芸術大学音楽学部作曲科卒業。2002年に音楽レーベルATAKを設立、国内外の先鋭的な電子音楽作品をリリースする。代表作にピアノ・ソロ・アルバム『ATAK015 for maria』『ATAK020 THE END』、パリ・シャトレ座でのソロ・コンサートを収録した『ATAK022 Live in Paris』など。また、映画『はじまりの記憶 杉本博司』、テレビドラマ『SPEC』など、数多くの映画やテレビドラマ、CMの音楽も担当。2012年には、初音ミク主演による映像とコンピュータ音響による人間不在のボーカロイドオペラ『THE END』をYCAMで発表。同作品は、その後、東京、パリ、アムステルダム、ハンブルク、オーフス、アブダビなどで公演が行われ、現在も世界中から上演要請を受けている。

ディレクター・アートディレクター・アーティスト
各種映像作品のディレクションや制作に加え、アートディレクション、イラストレーションやグラフィックデザインなど活動は多岐にわたる。トータルアートディレクションを目指した作品を数々リリースし、国内外の映画祭やイベントでも高く評価されている。初音ミク主演のボーカロイドオペラ『THE END』では、ルイ・ヴィトンと衣装コラボレーションを行い、全てのビジュアルディレクション・共同演出・映像ディレクターを務めた。
2016年に安室奈美恵 “NHKリオデジャネイロオリンピック・パラリンピック放送テーマソング” 『Hero』ミュージックビデオを手掛け、加えてアーティスト写真やジャケットなどの全てのビジュアルをディレクション。また、SMAPとのフェイスマッピングプロジェクトや安室奈美恵×GUCCI×VOGUEプロジェクト、攻殻機動隊ARISEのオープニング、現国立競技場クローズイベント映像演出や世界初OculusRiftを駆使したVRミュージックビデオをリリース、2014年にはソチオリンピック公式放送オープニングの演出などジャンルを超えた作品を数々生み出している。

サウンドアーティスト
先鋭的な電子音楽作品を発表し、国内外でインスタレーションやコンサートを行っている。立体音響インスタレーション『大きな耳をもったキツネ』や『hearing things #Metronome』では、暗闇のなかで音が生き物のように振る舞う現象を構築し、「耳で視る」という新たな聴覚体験を創出。サウンドアートの歴史を更新する重要作として、各界から高い評価を得ている。舞台や映画、公共空間においても、先端テクノロジーを用いた多彩な楽曲を提供したり、サウンドプロデュースを手掛けたりもしている。カンヌライオンズ国際クリエーティビティ・フェスティバルや文化庁メディア芸術祭での受賞歴多数。
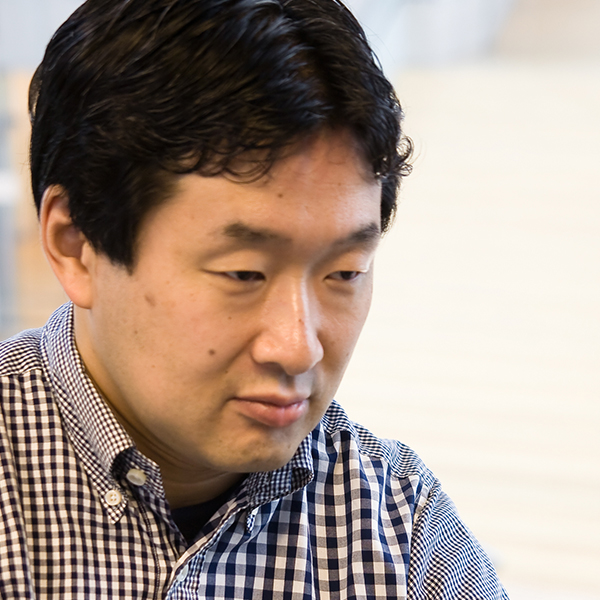
メディアアートキュレーター
90年代のメディアアートをリードした「キヤノン・アートラボ」にて、数多くのアートプロジェクトをプロデュースしたのち、コンセプトや制度設計から関わった山口情報芸術センター(YCAM)でチーフキュレーター、アーティスティックディレクターとして主催事業全般をディレクション、監修。渋谷慶一郎らによるボーカロイドオペラ『THE END』のプロデュースも手掛けた。アートセンターのあるべき姿を意識しながら、人材育成や場づくりにも積極的に取り組んでいる。

株式会社電通 ビジネス・クリエーション・センター レガシー事業推進室
ゼロ年代から都市開発に関わるなかで、都市のブランディングと文化発信の関係に興味を深める。当初は一人の観客として『THE END』を見ていたが、縁あって2015年のオランダ公演から“中の人”に。 各国の招聘公演での観客やメディアの反応から、『THE END』のテクノロジーアートとしての魅力に確信を得つつ、いまに至る。
2019/02/06
イヤホンをしているあなたは、もうサイボーグなのかも知れない(後編)
2017/08/15
2017/08/15
2024/11/15
まわり、まわって。Vol.7 日山豪氏
『音楽家とサウンドデザインの、まわり。』
2017/01/30