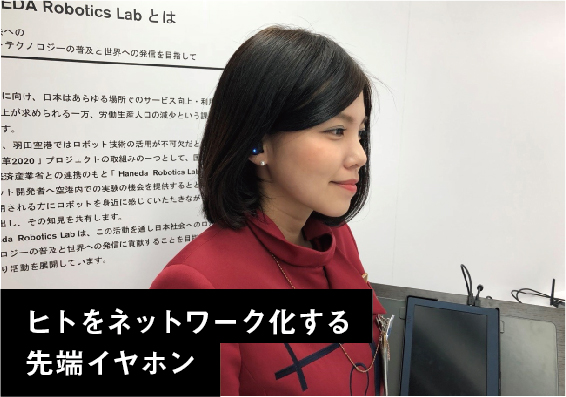2017/08/08
「アーティスト」と「アートディレクター」の境目はどこにあるのか(前編)
- November / 01 / 2017
何かを感じ取ってもらうには客観視が大切
舘鼻:清川さんと初めて会ったのは、確か4年か、5年くらい前でしたよね。シャネルのオートクチュールのショーで、たまたま席が隣になって…。それからは、いわゆるアーティスト友だちとして、お互いの展覧会に遊びに行ったり、来てもらったりしていますけど、まだ一緒に仕事をしたことはないし、なぜかあまりオフィシャルなところで関わることはなかったですね。
清川:そういえば、そうですね。こういう場でお話しするのも初めてですね。

舘鼻:だからこそ、今日は改めていろいろと聞いてみようと思っているのですが…(笑)、まず、清川さんといえば、写真に刺しゅうを施した作品がよく知られています。あれはいつ頃から始めたのですか?
清川:2003年くらいからです。当時は複製できないものに興味があって、いろいろと表現の可能性を模索していたんです。そうしたらある日、1枚の写真の上に糸が落ちているのを見かけて…。縫ってみよう、と思ったのがきっかけです。
舘鼻:学生の頃は何を?
清川:文化服装学院でアパレルデザインを専攻していました。でも、読者モデルみたいなこともしていたし、編集者と一緒に雑誌のページをつくったり、企画を提案したりもしていて、忙しい学生でしたね。
舘鼻:自分が被写体として表に出たりもしつつ、同時にディレクションしたり、プロデュースしたりもしていた、ということですか。周りのファッションデザイナーを目指している子たちとは、動き方が違っていたでしょう?
清川:全然違っていましたね。違いすぎて迷った時期もあったんですけど(笑)、そのまま活動を続けていたら、あるギャラリーに声を掛けてもらって、2001年に個展をやることになったんです。もともと卒業したらモデルの仕事は辞めようと思っていたのですが、ちょうどその頃から、CDジャケットをはじめ、デザインの仕事の依頼も来るようになって…。ギャラリーを中心に作品を発表しながら、一方で商業ベースの仕事も始めて、そこからはものづくり一本です。

「女である故に」 ©︎AsamiKiyokawa
舘鼻:ディレクションしてものをつくっていく仕事と、アーティストとして作品をつくっていく活動とは、似ているようで違いますよね。割と最初から両立できていたのですか?
清川:う〜ん、気付いてみたらそうだったという感じですね。ただ、学生の頃に自分がメディアに出たり、企画に関わったりしていたことも含めて、表と裏がよく見える立場にいることは、特にアーティスト活動に役立っているとは思います。例えば、普通ならメディアでは、女性のキラキラした表の部分だけを見せますよね。でも女性って、裏ではみんなコンプレックスを持っていて、本当はそれがすごく素敵だったりします。ずっと私が続けている「美女採集」(※)のシリーズも、そういう表と裏が見通せたからこそ始めたものでしたから。
※「美女採集」……美女の写真に刺しゅうなどによる装飾を施し、それぞれのイメージに合わせた動植物に変身させるシリーズ作品。

舘鼻:確かにあのシリーズは、一般に「こうだ」と思われている女優さんたちのイメージとは、ちょっと違った内面のようなものが見えてきて面白いですよね。それが清川さんの手の痕跡を残しつつ、表現されているのも興味深いし。“採集”されている女優さんの中には、あの企画で初めて会った人もいるのですか?
清川:むしろ、会ったことのない人を選んでいます。会ったことがあると、コンセプトが優しくなってしまうかなと思って。それに、そのとき世の中で輝いている美女を捕まえて標本にしているのは私ですけど、見る人にそこから何かを感じ取ってもらおうと思ったら、やっぱり客観視することが大切なので。
舘鼻:なるほど。分析はどうやって?
清川:全部、自分で調べます。リサーチ魔ですから(笑)。でも、映像を見れば、大体性格が分かります。この人はこうだなって。それを書き出していって、読み解いて、動植物に例えているんです。例えば、夏木マリさんだと、行動とか佇まいとかが、全て形状記憶されているような印象がありますよね。ずっと残り続けていきそうな。そういうイメージからアンモナイト。いま大人気の吉岡里帆ちゃんなら、いろんなものに巻きついて栄養を取り入れて、どんどん成長していく感じがアサガオかなと。橋本マナミさんは、ニシツノメドリですね。オレンジのくちばしを持った鳥で、一度にたくさんの魚を捕る。多くのものを一気に手に入れたいという積極的なところとか、そのための努力とかが橋本さんには見える気がして。

「美女採集」<吉岡里帆×朝顔> ©︎AsamiKiyokawa
舘鼻:あれだけたくさんの人を作品にしていると、モチーフがかぶったりしそうですけど……。
清川:いままで200人以上採集していますが、かぶったことはないですね。人の個性って、そのくらい多様なんだと思うんです。それに作品にしたくなるのは、その中でも面白い人ですから。この人、いいな、妖しいな、と思うような魅力のある人。これは「美女採集」だけの話ではありませんが、男性も女性も、経験とか年齢とかを重ねた人のほうが作品にはしやすいですね。
日本の工芸品は「用途のある芸術」だから
清川:ところで、舘鼻くんのデビューはいつなんですか?
舘鼻:いわゆる「世に知られるようになったきっかけ」ということで言えば、2009年につくっていた大学の卒業制作の作品ですね。清川さんもご存じのヒールレスシューズというかかとのない靴なのですが、それを2010年にレディー・ガガさんが日本のテレビ番組で履いて、僕のこともそこで話してくれたんです。それからしばらくは、レディー・ガガ専属のシューズメーカーとして、彼女としか仕事をしていなかったんですよ。もう、レディー・ガガさんのために人生を捧げているというくらい(笑)。

ヒールレスシューズ ©︎ NORITAKA TATEHANA, 2017
清川:初めて舘鼻くんと会ったときも、そんな感じでしたっけ?
舘鼻:たぶん、そうだったと思いますよ。ただ、僕自身は、別に靴をつくりたかったわけではないんです。僕は東京藝術大学の工芸科で染織を専攻してきていて、日本のファッションというべき着物や下駄について勉強したり、花魁(おいらん)の研究をしたりしながら、より新しい価値観が感じられる作品をつくりたいと思っていたんです。あのヒールレスシューズも花魁の高下駄から着想を得ました。

清川:私も花魁は大好きです。
舘鼻:彼女たちは江戸時代のファッションリーダーだったんですよね。いまストリートからファッションが発信されるといわれるのと同じで、当時は吉原の遊女の格好とか、メークとかが、江戸の町娘たちに取り入れられてはやったりしていたんです。皇室のような高貴なファッションももちろんあったわけですが、そういう高尚なものだけじゃなくて、不健全だからこそファッションになったようなところがあった。僕はそこに魅力を感じて、いくつも遊女に関わる作品をつくったりしています。例えば、ステンレスの大きなかんざしのオブジェとか。もともと日本の工芸品は「用途のある芸術」です。でも、いまは普段からそういうものを使っているわけじゃない。かんざしなんて、現代の人はあまり使いませんよね。そういう「用途のある芸術」から用途を取り去ったら、見る人にどういう感覚が芽生えるのか。彫刻として見たらどうなのか、という実験的な作品なんです。
清川:でも、ヒールレスシューズは、意外なくらいに履きやすいですよね。2012年に「VOGUE JAPAN Women of the Year」を受賞したときに、授賞式で履いて登壇させてもらいましたけど……。
舘鼻:日本の美術って、やっぱり工芸じゃないですか。いまも話したように、用途があって、それを満たしてこそという部分があるわけです。だから、かんざしのように昔からあるものをどうにかするのではなく、現代に新たに工芸品を生み出すのであれば、それはしっかりと使えるものであるべきだし、靴なら履きやすくて、歩けなくちゃいけない。そう思ってつくってはいますね。

かんざし ©︎ NORITAKA TATEHANA, 2017 Photo by GION
毎回のように新しい手法を開発する
清川:舘鼻くんは、他にもいろんな活動をされていますよね。少し前には文楽(※)にも関わっていたでしょう?
※文楽……浄瑠璃と人形によって演じる人形劇である人形浄瑠璃のうち、大阪を本拠とするもの。
舘鼻:パリのカルティエ現代美術財団で公演した「TATEHANA BUNRAKU : The Love Suicides on the Bridge」ですね。僕は監督を務めたんです。といっても、舞台美術もつくったり、演出もしたりと、いろんな作業に携わりましたけど。
清川:どういう経緯で公演をやることになったのですか?
舘鼻:フランスではもともと人形劇が盛んで、最初はフランスの人形劇の監督をしてみないか、というオファーをもらったんです。でも、日本にも人形浄瑠璃がありますから、どうせだったら、それを世界へ持っていきたいなと思ったんですよ。その提案を、カルティエ現代美術財団が受け止めてくれたんです。

文楽 ©︎ NORITAKA TATEHANA, 2017 Photo by GION
清川:準備が大変そうでしたよね。その時期は、なかなか連絡がつかなかったから…。
舘鼻:公演は2日間だけだったのですが、30人くらい連れて、日本から行きましたからね。一部は向こうで制作しましたし…。パリにアトリエを借りて、そこでチームと仕上げをしつつ、舞台を組み上げていったんです。
そういうところも含めて、あの公演は日本の世界観の世界への輸出のようなものでもあったのですが、日本とフランスは、歴史的な成り立ちとか、文化的な側面で似ているところもあるからか、現地の人たちには割とスムーズに受け入れられた気がします。ただ、同じことをニューヨークでやったらどうなるのかな、とは思いますね。パリでやったような心中の物語は、日本独自の死生観では文字通りのバッドエンドではないのだけど、アメリカ人はたぶん、もっとストレートに受け止めるでしょう? 今度はそこに切り込んでみたいなとは思っています。

清川:最近はレストランのクリエーティブディレクションもしているんでしょう? 本当に幅が広がってきていますね。
舘鼻:いや、でも、僕はまだ大学を卒業してから7年くらいしか活動していないんですよ。しかも前半はヒールレスシューズをつくるブランドとして活動していたわけですから、まだこれからです。
幅が広いという意味では、清川さんの活動は本当に多岐にわたっていますよね。CDジャケットのデザインをしたり、化粧品のパッケージデザインをしたり、広告のディレクションをしたり…。この間は、NHKの朝の連続テレビ小説の仕事もされていたでしょう?
清川:『べっぴんさん』(※)ですね。オープニング映像やメインビジュアルなどを手掛けていました。
※『べっぴんさん』……2016年10月から2017年4月にかけて放送されたNHK「連続テレビ小説」。子ども服を中心とするアパレルメーカー・ファミリアの創業者をモデルに、戦後の時代を生きる女性の姿が描かれた。

舘鼻:アーティストとしての活動も、さっき聞いた写真に刺しゅうを施す作品にしてもいろんなシリーズがあるし、絵本だって何冊も手掛けられていて…。本当にさまざまな表現をされていますよね。
清川:そうですね。光の彫刻をつくったりもしているし、いろんな手法を毎回、試行錯誤しながら開発しています。例えば、最近だと「1:1」という作品があるのですが、あれを実現させるのは、すごく苦労しました。

「Ⅰ:Ⅰ」<1月24日 Jan.24> ©︎AsamiKiyokawa
舘鼻:Instagramの写真を使った作品でしたよね。
清川:そうです、そうです。いまの時代って、特にSNSなどで自分が見ている世界は、実はたくさんのレイヤーでできているんじゃないかと私は思っていて、うそも本当も、見ている世界に全部隠れている気がするんです。そのことは1枚の写真にもいえるんじゃないかと思って…。それをどう表現しようかと考えたときに、あの手法を思いついたんです。
舘鼻:僕も実際に作品を拝見しましたけど、こんなの見たことがないと思いました。あれはどういう作業工程なんですか?
清川:詳しいことは秘密なんですけど(笑)、私がスマホで撮った写真をネガとポジに変換したものを、たくさん並べた糸に1本ずつ交互に転写して、それをアクリルの中に閉じ込めているんです。作業を進めていくときに職人さんに「こういうことをやりたい」と言ったら、最初は「やったことがないから」となかなか理解してもらえませんでしたが、最後は、面白いから一緒につくっていこうと協力していただけました。

清川あさみ
アーティスト
淡路島生まれ。2001年に初個展。03年より、写真に刺しゅうを施す手法を用いた作品制作を開始。水戸芸術館や東京・表参道ヒルズでの個展など、展覧会を全国で多数開催。 代表作に「美女採集」「Complex」シリーズ、絵本『銀河鉄道の夜』など。作家、谷川俊太郎氏との共作絵本『かみさまはいる いない?』が 2 年に一度のコングレス(児童書の世界大会)の日本代表に選ばれている。 「ベストデビュタント賞」受賞、VOCA展入賞、「VOGUE JAPAN Women of the Year」受賞、ASIAGRAPHアワード「創(つむぎ)賞」受賞。広告や空間など幅広いジャンルで国内外を問わず活躍している。現在は、福島ビエンナーレ「重陽の芸術祭」において、「智恵子抄」で著名な高村智恵子の生家でのインスタレーションも行っている。

舘鼻則孝
アーティスト
1985年、東京生まれ。歌舞伎町で銭湯「歌舞伎湯」を営む家系に生まれ、鎌倉で育つ。シュタイナー教育に基づく人形作家である母の影響で幼少期から手でものをつくることを覚える。東京藝術大学では絵画や彫刻を学び、後年は染織を専攻する。遊女に関する文化研究とともに日本の伝統的な染色技法である友禅染を用いた着物やげたの制作をする。近年はアーティストとして、国内外の展覧会へ参加する他、伝統工芸士との創作活動にも精力的に取り組んでいる。2016年3月には、カルティエ現代美術財団にて文楽の舞台を初監督し「TATEHANA BUNRAKU : The Love Suicides on the Bridge」を公演した。作品は、ニューヨークのメトロポリタン美術館やロンドンのビクトリア&アルバート博物館など、世界の著名な美術館に永久収蔵されている。
#Column
2017/08/22
2023/08/16
あらゆるイベントに最適な場を提供する、会場検索サービス「VENUE LINK」開発の舞台裏(後編)
2018/07/06
「ヒアラブル」の実験②~イヤホンで従業員をサポートする「サイバーアシスト」
2023/11/24
まわり、まわって。Vol.5 朝倉洋美氏
『アートとデザインの、まわり。』