2019/02/05
イヤホンをしているあなたは、もうサイボーグなのかも知れない(前編)
DENTSU LIVE | 電通ライブ
堀:ちなみに、今年もまたいろいろな改革を考えていらっしゃるんですか。
佐藤:今年は、ちょっとテクニカルな話になりますが、日本酒の造り方って明治以降はシンプルにしようとしてきたけれど、「新政」ではさらに複雑にしようと。伝統技術というのはどうしても複雑になるのです、いろんな菌を取り込むから。西洋科学だと、善玉菌と悪玉菌に分けて悪玉菌を皆殺しにする。東洋のやり方は、短絡的に善悪を問わないというか、ある特定の条件のもとだけで価値判断をしない。より自然に近い様々なフェーズの中で考えることで、悪玉菌にも最終的に良い働きをさせたりとか、視点を変えて可能性を引き出すことで、生命を利用しているという感じかな。
堀:人間の善玉コレステロール、悪玉コレステロールも一緒ですよね。どっちも必要ですよね。
佐藤:そう、どっちも必要なんですよ!自然の中には、不要な物ってないんです。科学が行き過ぎちゃうと、何でもかんでもコントロールしなきゃ気が済まなくて、気に入らないものを根絶しにかかるんですね。未来になって、あれは大事だったのに殺してしまったということが分かっても、取り返しがつかないですよ。
そういう意味では、日本酒は乳酸菌を悪玉菌扱いにしちゃったわけです。乳酸菌は一匹たりとも入れさせんと。江戸時代以前は乳酸菌の力をフル活用して素晴らしい発酵食品文化を創り上げてきたのに、突然、明治以降、酸味料を買ってきて入れればいいやという話が湧いて出た。しかも100年以上経った現代の酒造りにおいても、いまだに「乳酸菌は酒を腐らせる悪玉菌ですから要りません」となっている。実際にそうなんですよ。今でも大半の造り手はそう思っている。だから僕はいま、乳酸菌の肩を持とう、肩を持とうとしているわけです(笑)。
堀:むしろ乳酸菌推しで広告したら、女性はワインから日本酒にくら替えしますよ、絶対。発酵食品ブームですから。
佐藤:本当にそうだと思います。日本酒というのは、乳酸菌の扱いにかけては世界でもずば抜けた、神がかった技術を持っていたんですね、江戸時代までは。日本酒は研究室の中で造られていたんじゃない、現場で造られるんだ!
堀:映画のセリフみたいですね(笑)。
佐藤:それが、日本酒が売れなくなり、全体に均質化してしまった最大の理由です。僕にしたら、全部自前の伝統方式でやれよっていう話です、はっきり言えば。そうすれば、少なくとも自分らしい酒ができるはずです。それに、そのほうが本当のお客さんがつくと思うんです。
堀:「新政」の場合は、今、停滞した市場の中で、「自分らしいものを、自分らしい手法でつくる」というところが、競争を勝つポイントだったということですね。
佐藤:うん。でも、どちらかというと、競争に勝つというより、逆に誰とも競争したくなくて、こういう方向へ流れたというのが近いかもしれないです。
堀:「6号酵母」「生酛系酒母」「純米」「秋田県産米」にこだわって「新政」の酒は近年、立て続けに全国酒造鑑評会で金賞を受賞されました。それだけの成果を、佐藤さんが2007年くらいから始めて、10年に満たない時間で改革をなし遂げたというのは驚きですね。
佐藤:未知じゃないからね、酒造りって。江戸時代とかの文献を読み解いてやっている。ゼロからの勉強ではないから。
堀:それは「新政」の蔵に残った文献ですか?
佐藤:いや、アマゾンとかでも売ってますよ。古くて700年代から1600年くらいまでの文献は、一般にも少しは売られているんです。昔の酒造りの担い手というのはほとんど農民だったから、字が書けないので本が少ない。こういう本は、現場に入るのが好きな酔狂な蔵元なんかが隠れてつけたレシピのようなものなんですが、あってよかったと本当に思います。だから、未知のものを発明するわけではなく、過去の先達の道筋もあったし単に伝統に学んでいるだけなんです。誰にでもできることですよ。どこの蔵も4、5世代より前はやっていたのですから。僕じゃなくてもできるはずですよ。
堀:「新政」に触発された酒蔵が、改めて伝統的な江戸時代の手法でお酒を造る時代が、これからやって来るかもしれないですね。
佐藤:いま日本の酒蔵は1000社くらいしか生き残っていないから、これ以上減ってくると、世界的に展開していくにはちょっときつい。やっぱりある程度玉がそろっていないと、遺伝子多様性が低い動物みたいに、ちょっとしたことでみんなが死んでしまう。蔵がいっぱいあって、訳の分からない蔵がウジャウジャウジャウジャしているというのが、本当は健康な業界だと思う。
例えば、自分より教養が高い人にモノを売るのって超困難でしょ。特に酒のような嗜好品は。提供する側が、まず基本的なところでお客さんと同じところに立って、しかも酒文化ではちょっと目線が上にいることができてこそ、お客さんの人生を楽しませることができる。そういう意味では、日本酒はもっと社会性を高めないと新しいお客さんを取り込めないような気がします。これからの日本酒はもっと文化的に武装して、日本酒が世界に誇る醸造酒であることを広めてゆかねばならないと思います。日本酒の本質、哲学や世界観、倫理観を魅惑的に体現し、かつ説明することができるなら、世界中の誰しもがファンになってくれるはずと思います。たとえ一流の料理人やら食通やら、ソムリエやらバーテンダーやらが相手でも、感動させて一発で宗旨変えさせることだって難しくはないはずなんです。
堀:哲学、倫理ですか。
佐藤:それが一番、大切です。単に製法をすべて生酛に統一しただけでも、ワインになんか負けた気がしないわけですよ。「ワインは亜硫酸塩がないと発酵がなかなかうまくいかないし、日持ちもしませんよね。でも日本酒は一切何も加えなくても、健康な酒ができるんですよ。古今東西、日本酒こそ最高の自然派アルコール飲料なんです」って胸張って言える(笑)。ほかに例えばワインの世界の潮流を見ても、ビオディナミとか、テロワールとか、ナチュールとかの単語に代表される「自然との共存」みたいな考えが、ここ最近30~40年くらい盛り上がってきてます。でも、こうした考え方は、もともとは東洋が得意とする考えです。東洋は、特に日本はもっと自己のルーツに自信をもたなくてはいけない。前述のワインの用語なんかも、本来あんまり使う必要もないように思います。思想の核心部分については、一切借り物ではない。我々こそ本来知っていたはずのなんだから。僕はワインのソムリエに対しても、「日本酒をやってください」と言って堂々と勧めています。日本の酒を、日本の文化を、日本の言葉と文脈で語る機会も持って欲しいのです。

堀:お話を聞いていると、佐藤さんの酒造りは、確かに大改革ですね。
佐藤:僕は絵とか陶芸も好きですけれど、結局、江戸の物が一番世界で受けているような気がする。絵だってそうだし、和食、すしも完全に江戸文化が中心だからね。僕は日本酒のいろいろな製法をやるわけで、この間は生米こうじ(中国の紹興酒のこうじ)を作ったり、「菩提もと」という室町時代の製法に基づく酒をつくってみたりしてる。いろいろな時代の酒を試作してみたけど、結局、江戸より前の時代の日本酒って、中国や朝鮮の影響が非常に強い。言い方はきついけど、紹興酒の亜流のようなものを1000年遅れでやっているような感じなんです。ところが、江戸に入って鎖国してから、日本酒の製法は突然オリジナルになってゆくんです。日本人の創造性が爆発した感じです。生酛の手法なんかもそのひとつです。江戸はすごく良いです、真の「ザ・日本」なんですよ。ところがもったいないことに、明治になると途端に、鹿鳴館みたいな和洋折衷文化になってくる。ああゆうものは、あまり魅力的に感じません。見たければ、ヨーロッパに行けばもっとすごいホンモノが見られるわけですからね。
堀:面白いなあ(笑)。
佐藤:江戸は世界中の各国の文化の中でも、飛び抜けてエキセントリック。人類の多様性を思わせて素晴らしい。そういう優れた日本の文化を、自分のプロダクトにも取り入れていきたい。先祖がやっていたことなのですから、そんなに難しくもないはずです。
堀:製法を全部生酛に切りかえるというビジョンは、初めから描いていましたか。
佐藤:全部切りかえられたのは、厳密に言うと去年です。2012年から速醸はやめている。でも、江戸時代の方式の生酛にするにはものすごく人手もかかるから。利益があまり出ていなかったので、二人も三人もその部署につけることができなかったけれど、だんだん利益も出るようになったので、酒母のパートに人員をグッと集めて実現しました。
堀:こういう新しいお酒に対して、新しい飲み手たちがちゃんと育ち、選べる舌を持っているというのは、佐藤さんにとって励まされる材料ですね。
佐藤:そういうこと。僕は、才能あるいいファンが、日本酒文化をこれから支えていくと思って、そういう人のためにお酒を造って、そういう人たちに真っ先に届けるように工夫しています。
堀:ファンの才能か。僕も一人のファンとしてプレッシャーを感じますね。
佐藤:お客さんの能力が、きっとこのジャンル自体の実力になるんだと思う。
堀:今年、アーティストの村上隆さんとも、コラボレートされましたね。

Takashi Murakami×NEXT5
佐藤:村上隆さんがたいへん日本酒に理解が深くて、奇跡的にコラボレーションが実現しました。製法に生酛を採用したり、酒の内容面についても、村上さんとはよく相談させていただきましたね。あと、村上隆さんのファンの方や、日本酒に詳しくない方でも比較的楽に入手できるようにと配慮して、一般発売の機会を設けたんです。中野ブロードウェイ内にある「Bar Zingaro」という、村上隆さんが経営されているカフェで行いました。
堀:1店舗でしか売らなかったので、僕は朝から並んで買いに行きました。その瞬間から、前のほう100人ぐらい転売の人たちだらけで(笑)。外に止めてある、開けっ放しにしたバンに、どんどん積み込んでいっているわけです。その後10~20倍の値段が付きネット上で売られているのを見ると、なんだか心配になりました。

佐藤:そうなんだよね。結局、日本酒は全体に値付けが安いから、市場にゆがみが生じている。ワインは適正な値段で売っているから、そこまではならないでしょう。
堀:自由に値付けがされていけば、健全な価格で落ち着くわけですよね。
佐藤:うちは、ほぼすべて四合瓶しか造っていないんです。地元向きの常温対応の酒がちょっとありますが、それ以外一升瓶はない。その理由ですが、飲食店ですぐ飲み切られるようにです。昔から気になってたことがあって、それは日本酒よりも劣化しにくいワインのほうがよっぽど酸化を気にして扱われていることです。ワインバーではすぐ飲み切られるようにボトルサイズが基本。マグナムなんか買わない。温度管理以上に、常に瓶の中の空気を抜いたりと酸化への配慮をしている。一方、日本酒の世界はというと一升瓶ばかり。最近は冷蔵管理も浸透しましたが、何週間も瓶に飲み残しのままの酒が放置してある例もよく見ます。フレッシュで繊細な吟醸酒を扱う場合、開栓後のケアが重要。飲食店では四合瓶で回転率をあげたほうが客のためなんですが。しかしそうはなりにくい。なぜかというと一升瓶のほうが安いからです。メーカーが量の多い一升瓶をお得価格に設定しているんです。それでは市場は変わらない。そこで我々は一升瓶をやめることにしました。
堀:お客さんの手元に届くまでを厳しく管理しようとしたら、全てを直販するという手もありますよね。
佐藤:そうだね。ただ、酒販店も歴史がある産業だから。たとえば、ワインの業界でソムリエみたいなのは要らんと切ってしまったら、確かにソムリエが取っていた取り分はなくなるかもしれないけど、文化的には大ダメージになるじゃないですか。ソムリエでも酒販店でも、文化を伝えて第三者的に価値を高めてくれる機能はやっぱり要ると思うんです。
堀:だからこそ、酒販店は、ある程度選んでお付き合いをされていると。
佐藤:そういうこと。酒販店は、酒への知識、能力が高くて、そこに行けば僕のとこの酒がもっと良くお客さんに分かる、伝わる、そういう機能がないといけないよね。そうでないと、なんのために、店が蔵と客の間にいて、利益を得ることができるのか意味が通らなくなってしまう。酒販店を経由することで、より日本酒の魅力が増す、そういう相乗効果にならないといけません。そういう意味では、より若くて元気のある特約店の店主を私は常に応援しています。彼らを育成することは、日本酒業界の未来にとっても大切なことだと思っています。
堀:今日は改めて佐藤さんの酒造りの哲学を聞いて、大の日本酒ファンの僕も、目からウロコのことばかりでした。今後も注目し、どんどん飲んでいきますし応援しています。今日は本当に楽しかったです。ありがとうございました。

新政酒造 代表取締役社長
1974年秋田市生まれ。東京大学文学部卒業後、出版をはじめとする様々な職を経て、編集者、ジャーナリストとして活躍。 2005年に日本酒に開眼。06年より酒類総合研究所研究生、07年より生家の新政酒造へ入社。12年より同社代表取締役社長に就任。
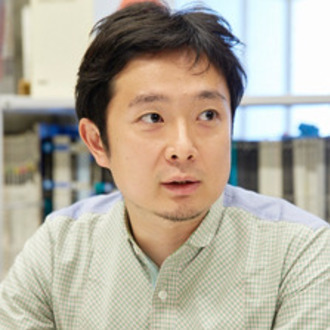
株式会社電通 電通ライブ
1982年生まれ。さいたま市育ち。早稲田大学理工学部建築学科卒業。 2006年電通入社。10年間OOHメディアのセールス、開発、プランニングに携わり2016年から現局に在籍。 国際会議における政府展示や大型展示会の企画・運営、ショップやショールームのディレクションが主な活動領域。1児の父。趣味は日本酒。
2019/02/05
イヤホンをしているあなたは、もうサイボーグなのかも知れない(前編)
2023/08/16
あらゆるイベントに最適な場を提供する、会場検索サービス「VENUE LINK」開発の舞台裏(前編)
2017/06/26
2017/08/09
2021/10/06
「ドバイ万博日本館」建築設計チームが語る、「つなぐ建築」に込めた想い(後編)