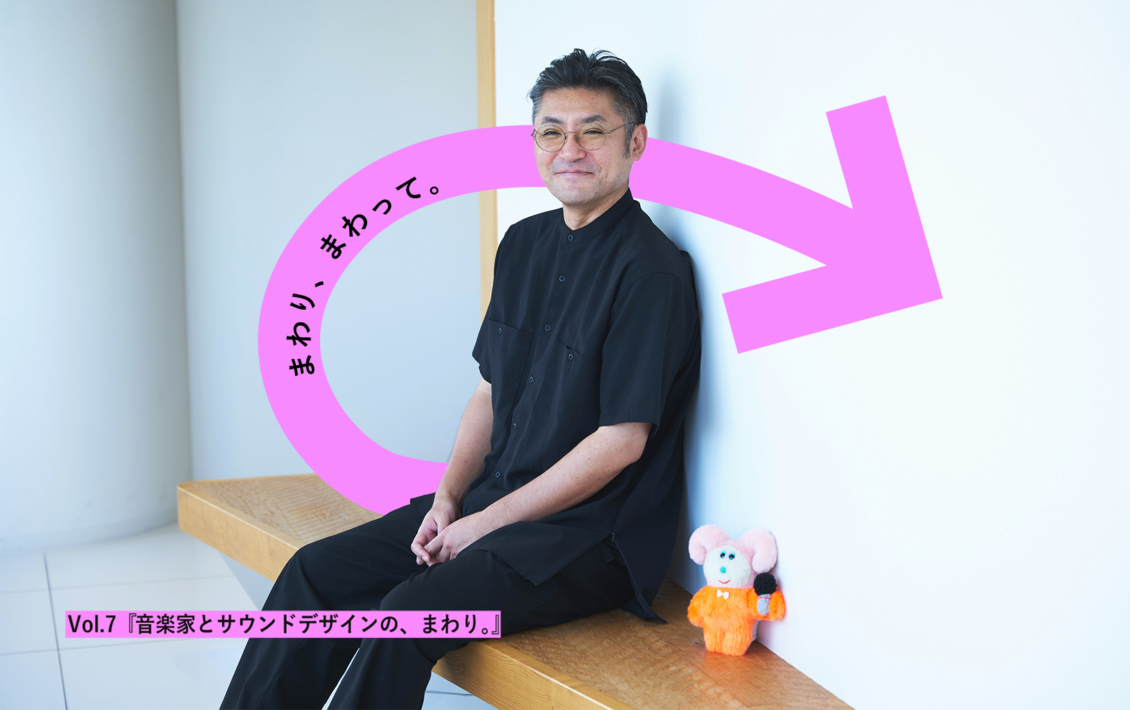2017/01/31
「アーティスト」と「アートディレクター」の境目はどこにあるのか(後編)
- November / 01 / 2017
自分が関わった作品を「分けない」
舘鼻:こうして改めてお互いの活動を振り返ってみると、かぶってはいないものの、似ているところもありますね。2人ともアーティストなんだけど、デザイナーや、アートディレクターの側面もありますし。
僕でいえば、さっきも話が出ましたけど、いまレストランのクリエーティブディレクションをしていて、ロゴのデザインやフードのディレクション、店内に置かれる彫刻作品の制作や建築デザインまで、全てに関わっています。そこにはアーティストの側面もあり、デザイナーとしての側面もあり、アートディレクターとしての側面もあるわけです。
清川さんにしても、針を持って写真に刺しゅうを施しているときはアーティストだけど、化粧品のパッケージデザインをしているときはデザイナーかもしれないし、広告で使うポスターのディレクションをしているときはアートディレクターですよね。清川さん自身は、そのあたりの境目はどう考えているのですか?
清川:そうですね…。逆に、舘鼻くんがいちばん最初に目指したのは、何だったんですか?
舘鼻:僕はファッションデザイナーを目指していたんです。で、そのときは、自分のファッションブランドがずっと残るようにしたいと思っていました。シャネルとか、カルティエみたいに、本人がいなくなってもブランドは存続するということです。
だけど、2010年のレディー・ガガさんの仕事がきっかけで、方向転換しようと思ったんですよ。作家になろうと思ったんです。どういうことかというと、僕は1985年に生まれて、いずれ何年かに死ぬわけですが、そうしたらそこで僕の時代は終わり、ということ。ファッションブランドだったら、死んでからも残るかもしれないけれど、作家だと舘鼻則孝が死んだら終わり。何年から何年までと区切られますよね。そうやって歴史に足あとを残すことのほうが、自分が求めている生き方に近いなと思うようになったんです。

清川:私はアーティストから始めたわけですけど、作品を見た人が、それをこういうところで使いたいと言ってくれたことで、デザイナーの仕事になっていきました。さらに、ものをつくるだけじゃなく、世界観そのものを表現してほしいと言われて、アートディレクターの仕事になっていったわけですが…、そういう変化が起こったそのときは混乱していましたね。だから、最初は自分の中では、それぞれを分けて活動していたんです。アーティストの作品とデザイナーの作品は違うって。
でも、分けなくてもいいんじゃないか、と最近は思うようになってきています。手を動かしてつくったものはもちろん作品だし、それこそ、いちばん最初は自分で自分を飾って表現していたわけですけど、それも作品だし、たくさんの人たちと一緒につくっていくものも作品だし…。全て自分が関わった作品だから、分ける必要はないんじゃないかと思うんですよ。
それに、いまは個人戦の時代じゃない気がしているんです。分かる人が分かればいい、ということではなくて、やっぱり伝わってこそだし、共有できてこそ、だと思う。何かしら、誰かに感じてもらうことが大切で、それが大きくなれば、みんなで時代をつくっていくようなことにもつながるのかなって。
舘鼻:僕らが生み出す作品は、コミュニケーションツールなんですよね。それを通して、何かを伝えたり、感じてもらったり、共有したりする。そのための装置を生み出している感覚が、僕の中にも非常に強くあります。だから単純に「靴をつくっています」ではなくて、その靴がどういう意味を持つのか、履いてくれた人が何を感じて、何を発信したくなるのか、ということまで考えます。いまこうやってしているおしゃべりも、もちろんコミュニケーションですが、作家にとっては、ものづくりはそれ以上にすごく有用なコミュニケーションの手段ですからね。
清川:本当にそう思います。私たちがしているのは、想像したことを形にして、見ている人にどこか余白を残すような仕事。どうして、ここにこれがあるんだろうとか、何でもいいんですけど、つくったものに触れた人が、余白の部分に何かを感じる。そういうことがすごく大事ですよね。

お客さまとの関係性が原動力
清川:ちなみに、舘鼻くんの原動力は何ですか?
舘鼻:お客さまとのサイクルですね。いまの僕の活動が靴から始まっているということもあるのですが、お客さまがいるということが当たり前なんですよ。だから、どういう作品にするのかも、注文されてから考えます。実際に面と向かって、お客さまと話し合うなかから作品を生み出しますから。
日本ではまだそこまで多くの人たちに履いていただいているわけじゃないんですけど、海外だとアメリカやイギリスなど、いろんなところで僕の靴を履いてくださっている人がいるんです。中には、僕がつくった靴しか履かないといってくださっている人も何人かいて、1回に30足とかオーダーされる。要するに、アーティストとパトロンの関係性です。
そういうお客さまが、わざわざ東京の青山にある僕のアトリエまで来てくれるわけですよ。そこでいろいろと話をして、どういう作品にするかを考えていく。で、出来上がったら、僕は必ず自分でお客さまのところまで届けにいくんです。まあ、そこで新しいオーダーをもらって帰ったりもするのですが(笑)、大体そういうサイクルなんです。でも、このサイクルは1人ではまわらなくて、自分とお客さまとのリレーションシップで成り立っています。その関係性が僕の原動力になっていると思いますね。

清川:私は普段の生活の中で、ニュースを見たりいろんなことをしているときに、必ず何か矛盾を感じるんですよ。自分と何かのギャップとか。それが作品になりやすいですね。
舘鼻:自分の感情は常に変化するわけですけど、それを形にしていくのが作家ですから。作品というツールを通じて、僕らはさまざまな想いを共有しようとしているのでしょうね。
挑戦することは僕らの仕事
舘鼻:あと、実は僕には前からすごく気になっていることがあるので、最後に聞きたいのですが、清川さんはその小さな体で、あれだけたくさんの仕事をしているわけですよね。どうやって時間をつくって仕事をしているのかなって、5年くらい前からずっと思っているんですよ(笑)。実際のところ、どういう毎日を送っているのですか?
清川:私、朝は5時に起きるんです。子どもが起きてしまうということもあるんですけど、もともと早起きなんですよ。起きてすぐ、子どものことをいろいろやって、それからメールをチェックしたりするのですが、いちばんアイデアが浮かんだり、ラフスケッチがはかどったりするのは、その後ですね。

舘鼻:それは何時から何時くらいの話ですか?
清川:自分が飽きるまでやるんですけど、大体、午前中です。アトリエに行くときもあるし、自宅のこともあるのですが、ただアイデアが浮かびやすいのは移動中なんです。そこでふわっといろいろ浮かんで、書き留めるのが次の日の朝、という感じですね。
舘鼻:アイデアが浮かんだときにメモを取るわけじゃないんですか?
清川:メモを取ってもなくしてしまうんですよ、私(笑)。でも、いいアイデアは必ず覚えていますから。
舘鼻:浮かんだアイデアは、割とすぐに作品化するのですか?
清川:そこはうまく言葉にできないのですが、頭の中に構造ができて、プロセスが決まって、ゴールが決まったら、作品にします。自分にしか分からない世界ですけど(笑)。ただ、その頭の中にあるものを周りに伝えるのが大変で…。
舘鼻:ああ、それは分かります。清川さんもそうだし、僕もそうなのですが、チームで動くじゃないですか。いろんな人に関わってもらうわけだから、ビジョンを共有しなくてはいけないのだけど、それを説明するのは大変ですよね。いつも葛藤の連続です。
清川:私もそうです。自分の中のゴールはここなのに、まだここにいる、どうしようって、いつも思っています。しかも、それが何個もあるし…。形にしていくのって、本当に大変ですよね。
舘鼻:とはいえ、こうして実際に会うと、清川さんはすごく優雅な時間を過ごしているように見えるんですよ。いつ忙しくしているのかなと不思議なんですけど、夜中まで仕事をしているのですか?
清川:夜中は必ず寝ています(笑)。5時に起きますから。だから、やっぱり朝ですね。朝の仕事のスピードは本当にすごくて、そこで全て終わらせるというくらいの速さでやっています。
あと、100点でなくてもいい、と思うようにはしていますね。放っておくと、120パーセントのクオリティーを追い求めてしまうほうなので、そのくらいの気持ちでいるのがちょうどいいんです。全てのことに飛び込むわけにはいかないので。さっきもお話ししたように、職人さんに「意味が分からない」と言われながらもアクリルに糸を閉じ込めたりして(笑)、毎回、新しいことに挑戦していますから。

舘鼻:挑戦することは、僕らの仕事ですからね。
清川:さっきも話したように、そこを理解してもらってチームでつくっていくのは本当に大変なんですけど、でも乗り越えて、作品を形にして、新しい世界が広がったときにはすごくうれしいんですよね。だからやめられないのかな、とも思いますけど。
舘鼻:よく分かります。僕のヒールレスシューズにしてもそうですが、実際に体験した感覚が予想していたものと違うと、みんな驚くわけです。そうやって新しい価値観を感じてもらえるような場を提供できたときは、本当にうれしいですよね。
(了)

清川あさみ
アーティスト
淡路島生まれ。2001年に初個展。03年より、写真に刺しゅうを施す手法を用いた作品制作を開始。水戸芸術館や東京・表参道ヒルズでの個展など、展覧会を全国で多数開催。 代表作に「美女採集」「Complex」シリーズ、絵本『銀河鉄道の夜』など。作家、谷川俊太郎氏との共作絵本『かみさまはいる いない?』が 2 年に一度のコングレス(児童書の世界大会)の日本代表に選ばれている。 「ベストデビュタント賞」受賞、VOCA展入賞、「VOGUE JAPAN Women of the Year」受賞、ASIAGRAPHアワード「創(つむぎ)賞」受賞。広告や空間など幅広いジャンルで国内外を問わず活躍している。現在は、福島ビエンナーレ「重陽の芸術祭」において、「智恵子抄」で著名な高村智恵子の生家でのインスタレーションも行っている。

舘鼻則孝
アーティスト
1985年、東京生まれ。歌舞伎町で銭湯「歌舞伎湯」を営む家系に生まれ、鎌倉で育つ。シュタイナー教育に基づく人形作家である母の影響で幼少期から手でものをつくることを覚える。東京藝術大学では絵画や彫刻を学び、後年は染織を専攻する。遊女に関する文化研究とともに日本の伝統的な染色技法である友禅染を用いた着物やげたの制作をする。近年はアーティストとして、国内外の展覧会へ参加する他、伝統工芸士との創作活動にも精力的に取り組んでいる。2016年3月には、カルティエ現代美術財団にて文楽の舞台を初監督し「TATEHANA BUNRAKU : The Love Suicides on the Bridge」を公演した。作品は、ニューヨークのメトロポリタン美術館やロンドンのビクトリア&アルバート博物館など、世界の著名な美術館に永久収蔵されている。