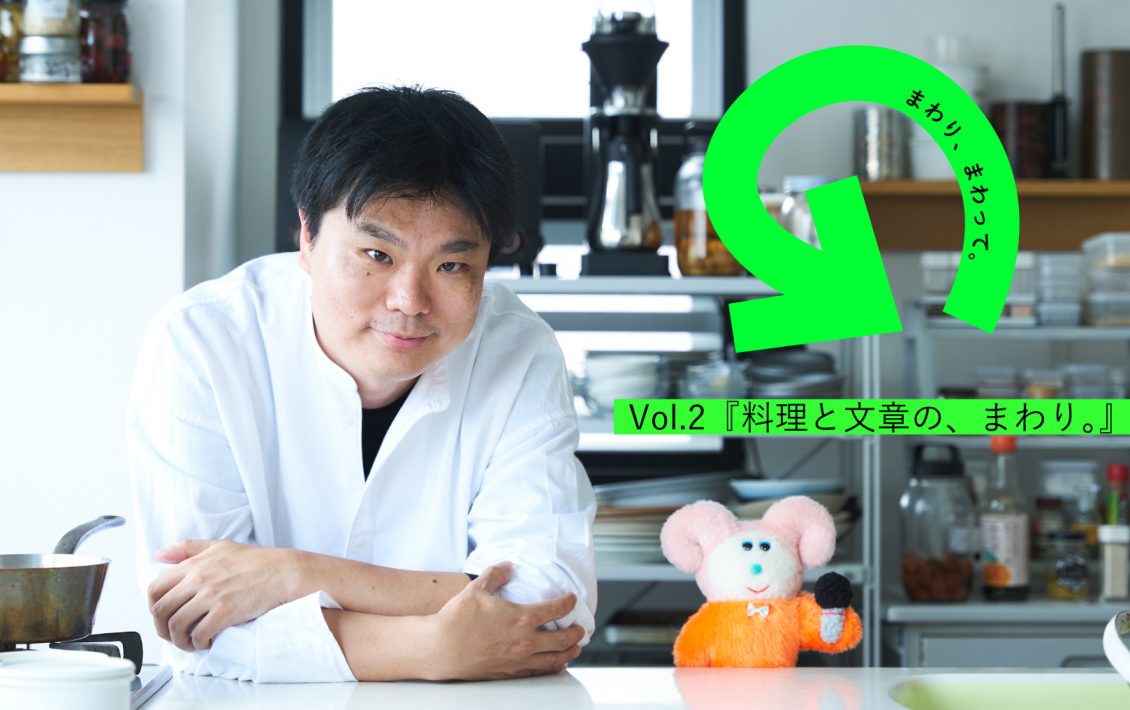2017/05/24
HAPPY HAPPY HAPPY END LUMINE CHRISTMAS 2018
- 株式会社ルミネ
- December / 25 / 2018
- ルミネエスト新宿/ルミネ池袋/ルミネ新宿/ルミネ有楽町/ルミネ大宮/ルミネ立川/ルミネ横浜/ルミネ荻窪/ルミネ北千住/ルミネ町田/ルミネ川越/ルミネ藤沢
ルミネクリスマスキャンペーン「HAPPY HAPPY HAPPY END」
1年の終わりにあるクリスマスに、「ハッピーエンドにしませんか。」と呼び掛けるべく、「HAPPY HAPPY HAPPY END」というコンセプトでキャンペーンを設計。ルミネを「ハッピーエンド」を作り出す工場に見立てたクリエーティブで、ルミネ全館の館内装飾・空間デザインを展開。
■商業施設が持つ空間のポテンシャルを最大限に引き出す、
3DCGで世界を構築する新たなクリエーティブアプローチを開発。
今回のキャンペーンでは、「ルミネ=ハッピーエンドを作る工場」と設定し、その工場自体を3DCG(※)で創造するというアプローチをとった。
クリエーターには、3D visual designを軸に国内外の広告・キャラクターデザイン・映像を手掛ける豊田遼吾氏を起用。
3DCGを駆使することで、自由にアングルを変えて書き出すことが可能となり、エントランス・エスカレーター・エレベーター・タペストリー等々、各施設の要望を聞きながらそれぞれの装飾面に最適化した表情を作り出すことを実現。
さらに、ショーウインドウ等の立体物では、3DCG世界の一部をそのままリアルに再現。
また、デジタルサイネージでは、3DCGのさまざまなパーツをアニメーション化して、複数展開。館全体を、ハッピーエンドに相応しい、賑やかで楽しい世界に塗り替えることに挑戦した。
※3DCG(3次元コンピュータグラフィックス)とは…コンピュータの演算によって3次元空間内の仮想的な立体物を2次元である平面上の情報に変換することで奥行き感のある画像を作る手法










HAPPY HAPPY HAPPY END LUMINE CHRISTMAS 2018
株式会社ルミネ
2018年11月13日(火)~12月25日(月)
ルミネエスト新宿/ルミネ池袋/ルミネ新宿/ルミネ有楽町/ルミネ大宮/ルミネ立川/ルミネ横浜/ルミネ荻窪/ルミネ北千住/ルミネ町田/ルミネ川越/ルミネ藤沢
GINZA SIX 開業イベント
- GINZA SIX(J フロント リテイング株式会社、森ビル株式会社、L キャタルトン リアルエステート、住友商事株式会社)
- April / 20 / 2017
- GINZA SIX
Where luxury begins 世界が次に望むものを
4月20日に開業した東京・銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」のオープニングイベント。「Life At Its Best 最高に満たされた暮らし」をコンセプトに、一商業施設の開業にとどまらず、世界でここにしかない特別な場と仕掛けを創発し新たな価値「New Luxury」を体感してもらうための開業プログラムを実施。
■オープニングセレモニー
入居前のオフィス1フロア分を使用して実施。CM上映、主催挨拶、来賓挨拶のみのシンプルな進行ながら、来賓挨拶を安倍首相や小池都知事が務め話題に。多数の現役閣僚や国会議員、大使、経済界トップなど約600名が出席。
■内覧パーティー
オープニングセレモニーの招待者に加えて、文化人、インフルエンサー、4事業者関係先、等約4000名が来場。商業施設(B2F-6F、13F一部)・屋上・観世能楽堂の内覧を行うとともに、2F吹抜け下での生演奏やフォトスポットの設置、各フロアではドリンク&スイーツを提供。
■内覧会
4事業者およびテナントの顧客を招待しての内覧会を実施。(招待者運営のみ)
■店舗レセプション
各テナント主催によるレセプションを実施。(招待者運営のみ)
■グランドオープン テープカット
開業当日、4事業者代表と中央区区長、銀座通連合会会長が登壇して、テープカットセレモニーを実施。












GINZA SIX 開業イベント
GINZA SIX(J フロント リテイング株式会社、森ビル株式会社、L キャタルトン リアルエステート、住友商事株式会社)
2017年4月17日~4月20日
GINZA SIX
世界一の壁を越えろ
au CLIMBING FES
- KDDI株式会社
- January / 22 / 2017
- 二子玉川ライズ ガレリア
au 初のスポーツクライミングイベント「au CLIMBING FES」の企画・運営
初めての方から経験者まで、いま注目のスポーツクライミングが楽しめるイベント『au CLIMIBING FES』を開催。「IFSCクライミング世界選手権パリ2016大会」の決勝で使われ楢﨑選手が制覇した「世界選手権の壁」をauが忠実に再現。
■キックオフイベント
「IFSCクライミング世界選手権パリ2016大会」で日本人初のチャンピオンかつTEAM auのメンバーである楢﨑智亜選手とゲストタレントの魔裟斗さん・朝比奈彩さんがキックオフイベントに登場。楢﨑選手にレクチャーを受けながら魔裟斗さん・朝比奈彩さんもクライミングにチャレンジ。
■一般体験イベント(世界選手権の壁)
auが忠実に再現した「世界選手権の壁」に我こそは!と自信のあるクライマー達が果敢に挑戦。4日間で計3名の完登者が誕生。会場からは多くの歓声と称賛の拍手が鳴り響いた。
■一般体験イベント(初級者の壁)
会場内には、世界選手権の壁以外にも初級者・中級者の壁を用意。小さな子供から(安全対策上対象は小学生以上)、中高生、大人まで多くの方々がチャレンジ。未経験者でも気軽にクライミングに参加し楽しんでいた。
■フォトスポットコーナー
難関の壁を模したトリックアート風フォトスポットと表彰台を設置。クライマーだけでなく、子供から大人まで多くの家族連れが楽しめる環境を提供。




世界一の壁を越えろ
au CLIMBING FES
KDDI株式会社
2017年1月19日~22日
二子玉川ライズ ガレリア
「アーティスト」と「アートディレクター」の境目はどこにあるのか(前編)
- November / 01 / 2017
何かを感じ取ってもらうには客観視が大切
舘鼻:清川さんと初めて会ったのは、確か4年か、5年くらい前でしたよね。シャネルのオートクチュールのショーで、たまたま席が隣になって…。それからは、いわゆるアーティスト友だちとして、お互いの展覧会に遊びに行ったり、来てもらったりしていますけど、まだ一緒に仕事をしたことはないし、なぜかあまりオフィシャルなところで関わることはなかったですね。
清川:そういえば、そうですね。こういう場でお話しするのも初めてですね。

舘鼻:だからこそ、今日は改めていろいろと聞いてみようと思っているのですが…(笑)、まず、清川さんといえば、写真に刺しゅうを施した作品がよく知られています。あれはいつ頃から始めたのですか?
清川:2003年くらいからです。当時は複製できないものに興味があって、いろいろと表現の可能性を模索していたんです。そうしたらある日、1枚の写真の上に糸が落ちているのを見かけて…。縫ってみよう、と思ったのがきっかけです。
舘鼻:学生の頃は何を?
清川:文化服装学院でアパレルデザインを専攻していました。でも、読者モデルみたいなこともしていたし、編集者と一緒に雑誌のページをつくったり、企画を提案したりもしていて、忙しい学生でしたね。
舘鼻:自分が被写体として表に出たりもしつつ、同時にディレクションしたり、プロデュースしたりもしていた、ということですか。周りのファッションデザイナーを目指している子たちとは、動き方が違っていたでしょう?
清川:全然違っていましたね。違いすぎて迷った時期もあったんですけど(笑)、そのまま活動を続けていたら、あるギャラリーに声を掛けてもらって、2001年に個展をやることになったんです。もともと卒業したらモデルの仕事は辞めようと思っていたのですが、ちょうどその頃から、CDジャケットをはじめ、デザインの仕事の依頼も来るようになって…。ギャラリーを中心に作品を発表しながら、一方で商業ベースの仕事も始めて、そこからはものづくり一本です。

「女である故に」 ©︎AsamiKiyokawa
舘鼻:ディレクションしてものをつくっていく仕事と、アーティストとして作品をつくっていく活動とは、似ているようで違いますよね。割と最初から両立できていたのですか?
清川:う〜ん、気付いてみたらそうだったという感じですね。ただ、学生の頃に自分がメディアに出たり、企画に関わったりしていたことも含めて、表と裏がよく見える立場にいることは、特にアーティスト活動に役立っているとは思います。例えば、普通ならメディアでは、女性のキラキラした表の部分だけを見せますよね。でも女性って、裏ではみんなコンプレックスを持っていて、本当はそれがすごく素敵だったりします。ずっと私が続けている「美女採集」(※)のシリーズも、そういう表と裏が見通せたからこそ始めたものでしたから。
※「美女採集」……美女の写真に刺しゅうなどによる装飾を施し、それぞれのイメージに合わせた動植物に変身させるシリーズ作品。

舘鼻:確かにあのシリーズは、一般に「こうだ」と思われている女優さんたちのイメージとは、ちょっと違った内面のようなものが見えてきて面白いですよね。それが清川さんの手の痕跡を残しつつ、表現されているのも興味深いし。“採集”されている女優さんの中には、あの企画で初めて会った人もいるのですか?
清川:むしろ、会ったことのない人を選んでいます。会ったことがあると、コンセプトが優しくなってしまうかなと思って。それに、そのとき世の中で輝いている美女を捕まえて標本にしているのは私ですけど、見る人にそこから何かを感じ取ってもらおうと思ったら、やっぱり客観視することが大切なので。
舘鼻:なるほど。分析はどうやって?
清川:全部、自分で調べます。リサーチ魔ですから(笑)。でも、映像を見れば、大体性格が分かります。この人はこうだなって。それを書き出していって、読み解いて、動植物に例えているんです。例えば、夏木マリさんだと、行動とか佇まいとかが、全て形状記憶されているような印象がありますよね。ずっと残り続けていきそうな。そういうイメージからアンモナイト。いま大人気の吉岡里帆ちゃんなら、いろんなものに巻きついて栄養を取り入れて、どんどん成長していく感じがアサガオかなと。橋本マナミさんは、ニシツノメドリですね。オレンジのくちばしを持った鳥で、一度にたくさんの魚を捕る。多くのものを一気に手に入れたいという積極的なところとか、そのための努力とかが橋本さんには見える気がして。

「美女採集」<吉岡里帆×朝顔> ©︎AsamiKiyokawa
舘鼻:あれだけたくさんの人を作品にしていると、モチーフがかぶったりしそうですけど……。
清川:いままで200人以上採集していますが、かぶったことはないですね。人の個性って、そのくらい多様なんだと思うんです。それに作品にしたくなるのは、その中でも面白い人ですから。この人、いいな、妖しいな、と思うような魅力のある人。これは「美女採集」だけの話ではありませんが、男性も女性も、経験とか年齢とかを重ねた人のほうが作品にはしやすいですね。
日本の工芸品は「用途のある芸術」だから
清川:ところで、舘鼻くんのデビューはいつなんですか?
舘鼻:いわゆる「世に知られるようになったきっかけ」ということで言えば、2009年につくっていた大学の卒業制作の作品ですね。清川さんもご存じのヒールレスシューズというかかとのない靴なのですが、それを2010年にレディー・ガガさんが日本のテレビ番組で履いて、僕のこともそこで話してくれたんです。それからしばらくは、レディー・ガガ専属のシューズメーカーとして、彼女としか仕事をしていなかったんですよ。もう、レディー・ガガさんのために人生を捧げているというくらい(笑)。

ヒールレスシューズ ©︎ NORITAKA TATEHANA, 2017
清川:初めて舘鼻くんと会ったときも、そんな感じでしたっけ?
舘鼻:たぶん、そうだったと思いますよ。ただ、僕自身は、別に靴をつくりたかったわけではないんです。僕は東京藝術大学の工芸科で染織を専攻してきていて、日本のファッションというべき着物や下駄について勉強したり、花魁(おいらん)の研究をしたりしながら、より新しい価値観が感じられる作品をつくりたいと思っていたんです。あのヒールレスシューズも花魁の高下駄から着想を得ました。

清川:私も花魁は大好きです。
舘鼻:彼女たちは江戸時代のファッションリーダーだったんですよね。いまストリートからファッションが発信されるといわれるのと同じで、当時は吉原の遊女の格好とか、メークとかが、江戸の町娘たちに取り入れられてはやったりしていたんです。皇室のような高貴なファッションももちろんあったわけですが、そういう高尚なものだけじゃなくて、不健全だからこそファッションになったようなところがあった。僕はそこに魅力を感じて、いくつも遊女に関わる作品をつくったりしています。例えば、ステンレスの大きなかんざしのオブジェとか。もともと日本の工芸品は「用途のある芸術」です。でも、いまは普段からそういうものを使っているわけじゃない。かんざしなんて、現代の人はあまり使いませんよね。そういう「用途のある芸術」から用途を取り去ったら、見る人にどういう感覚が芽生えるのか。彫刻として見たらどうなのか、という実験的な作品なんです。
清川:でも、ヒールレスシューズは、意外なくらいに履きやすいですよね。2012年に「VOGUE JAPAN Women of the Year」を受賞したときに、授賞式で履いて登壇させてもらいましたけど……。
舘鼻:日本の美術って、やっぱり工芸じゃないですか。いまも話したように、用途があって、それを満たしてこそという部分があるわけです。だから、かんざしのように昔からあるものをどうにかするのではなく、現代に新たに工芸品を生み出すのであれば、それはしっかりと使えるものであるべきだし、靴なら履きやすくて、歩けなくちゃいけない。そう思ってつくってはいますね。

かんざし ©︎ NORITAKA TATEHANA, 2017 Photo by GION
毎回のように新しい手法を開発する
清川:舘鼻くんは、他にもいろんな活動をされていますよね。少し前には文楽(※)にも関わっていたでしょう?
※文楽……浄瑠璃と人形によって演じる人形劇である人形浄瑠璃のうち、大阪を本拠とするもの。
舘鼻:パリのカルティエ現代美術財団で公演した「TATEHANA BUNRAKU : The Love Suicides on the Bridge」ですね。僕は監督を務めたんです。といっても、舞台美術もつくったり、演出もしたりと、いろんな作業に携わりましたけど。
清川:どういう経緯で公演をやることになったのですか?
舘鼻:フランスではもともと人形劇が盛んで、最初はフランスの人形劇の監督をしてみないか、というオファーをもらったんです。でも、日本にも人形浄瑠璃がありますから、どうせだったら、それを世界へ持っていきたいなと思ったんですよ。その提案を、カルティエ現代美術財団が受け止めてくれたんです。

文楽 ©︎ NORITAKA TATEHANA, 2017 Photo by GION
清川:準備が大変そうでしたよね。その時期は、なかなか連絡がつかなかったから…。
舘鼻:公演は2日間だけだったのですが、30人くらい連れて、日本から行きましたからね。一部は向こうで制作しましたし…。パリにアトリエを借りて、そこでチームと仕上げをしつつ、舞台を組み上げていったんです。
そういうところも含めて、あの公演は日本の世界観の世界への輸出のようなものでもあったのですが、日本とフランスは、歴史的な成り立ちとか、文化的な側面で似ているところもあるからか、現地の人たちには割とスムーズに受け入れられた気がします。ただ、同じことをニューヨークでやったらどうなるのかな、とは思いますね。パリでやったような心中の物語は、日本独自の死生観では文字通りのバッドエンドではないのだけど、アメリカ人はたぶん、もっとストレートに受け止めるでしょう? 今度はそこに切り込んでみたいなとは思っています。

清川:最近はレストランのクリエーティブディレクションもしているんでしょう? 本当に幅が広がってきていますね。
舘鼻:いや、でも、僕はまだ大学を卒業してから7年くらいしか活動していないんですよ。しかも前半はヒールレスシューズをつくるブランドとして活動していたわけですから、まだこれからです。
幅が広いという意味では、清川さんの活動は本当に多岐にわたっていますよね。CDジャケットのデザインをしたり、化粧品のパッケージデザインをしたり、広告のディレクションをしたり…。この間は、NHKの朝の連続テレビ小説の仕事もされていたでしょう?
清川:『べっぴんさん』(※)ですね。オープニング映像やメインビジュアルなどを手掛けていました。
※『べっぴんさん』……2016年10月から2017年4月にかけて放送されたNHK「連続テレビ小説」。子ども服を中心とするアパレルメーカー・ファミリアの創業者をモデルに、戦後の時代を生きる女性の姿が描かれた。

舘鼻:アーティストとしての活動も、さっき聞いた写真に刺しゅうを施す作品にしてもいろんなシリーズがあるし、絵本だって何冊も手掛けられていて…。本当にさまざまな表現をされていますよね。
清川:そうですね。光の彫刻をつくったりもしているし、いろんな手法を毎回、試行錯誤しながら開発しています。例えば、最近だと「1:1」という作品があるのですが、あれを実現させるのは、すごく苦労しました。

「Ⅰ:Ⅰ」<1月24日 Jan.24> ©︎AsamiKiyokawa
舘鼻:Instagramの写真を使った作品でしたよね。
清川:そうです、そうです。いまの時代って、特にSNSなどで自分が見ている世界は、実はたくさんのレイヤーでできているんじゃないかと私は思っていて、うそも本当も、見ている世界に全部隠れている気がするんです。そのことは1枚の写真にもいえるんじゃないかと思って…。それをどう表現しようかと考えたときに、あの手法を思いついたんです。
舘鼻:僕も実際に作品を拝見しましたけど、こんなの見たことがないと思いました。あれはどういう作業工程なんですか?
清川:詳しいことは秘密なんですけど(笑)、私がスマホで撮った写真をネガとポジに変換したものを、たくさん並べた糸に1本ずつ交互に転写して、それをアクリルの中に閉じ込めているんです。作業を進めていくときに職人さんに「こういうことをやりたい」と言ったら、最初は「やったことがないから」となかなか理解してもらえませんでしたが、最後は、面白いから一緒につくっていこうと協力していただけました。

清川あさみ
アーティスト
淡路島生まれ。2001年に初個展。03年より、写真に刺しゅうを施す手法を用いた作品制作を開始。水戸芸術館や東京・表参道ヒルズでの個展など、展覧会を全国で多数開催。 代表作に「美女採集」「Complex」シリーズ、絵本『銀河鉄道の夜』など。作家、谷川俊太郎氏との共作絵本『かみさまはいる いない?』が 2 年に一度のコングレス(児童書の世界大会)の日本代表に選ばれている。 「ベストデビュタント賞」受賞、VOCA展入賞、「VOGUE JAPAN Women of the Year」受賞、ASIAGRAPHアワード「創(つむぎ)賞」受賞。広告や空間など幅広いジャンルで国内外を問わず活躍している。現在は、福島ビエンナーレ「重陽の芸術祭」において、「智恵子抄」で著名な高村智恵子の生家でのインスタレーションも行っている。

舘鼻則孝
アーティスト
1985年、東京生まれ。歌舞伎町で銭湯「歌舞伎湯」を営む家系に生まれ、鎌倉で育つ。シュタイナー教育に基づく人形作家である母の影響で幼少期から手でものをつくることを覚える。東京藝術大学では絵画や彫刻を学び、後年は染織を専攻する。遊女に関する文化研究とともに日本の伝統的な染色技法である友禅染を用いた着物やげたの制作をする。近年はアーティストとして、国内外の展覧会へ参加する他、伝統工芸士との創作活動にも精力的に取り組んでいる。2016年3月には、カルティエ現代美術財団にて文楽の舞台を初監督し「TATEHANA BUNRAKU : The Love Suicides on the Bridge」を公演した。作品は、ニューヨークのメトロポリタン美術館やロンドンのビクトリア&アルバート博物館など、世界の著名な美術館に永久収蔵されている。
「アーティスト」と「アートディレクター」の境目はどこにあるのか(後編)
- November / 01 / 2017
自分が関わった作品を「分けない」
舘鼻:こうして改めてお互いの活動を振り返ってみると、かぶってはいないものの、似ているところもありますね。2人ともアーティストなんだけど、デザイナーや、アートディレクターの側面もありますし。
僕でいえば、さっきも話が出ましたけど、いまレストランのクリエーティブディレクションをしていて、ロゴのデザインやフードのディレクション、店内に置かれる彫刻作品の制作や建築デザインまで、全てに関わっています。そこにはアーティストの側面もあり、デザイナーとしての側面もあり、アートディレクターとしての側面もあるわけです。
清川さんにしても、針を持って写真に刺しゅうを施しているときはアーティストだけど、化粧品のパッケージデザインをしているときはデザイナーかもしれないし、広告で使うポスターのディレクションをしているときはアートディレクターですよね。清川さん自身は、そのあたりの境目はどう考えているのですか?
清川:そうですね…。逆に、舘鼻くんがいちばん最初に目指したのは、何だったんですか?
舘鼻:僕はファッションデザイナーを目指していたんです。で、そのときは、自分のファッションブランドがずっと残るようにしたいと思っていました。シャネルとか、カルティエみたいに、本人がいなくなってもブランドは存続するということです。
だけど、2010年のレディー・ガガさんの仕事がきっかけで、方向転換しようと思ったんですよ。作家になろうと思ったんです。どういうことかというと、僕は1985年に生まれて、いずれ何年かに死ぬわけですが、そうしたらそこで僕の時代は終わり、ということ。ファッションブランドだったら、死んでからも残るかもしれないけれど、作家だと舘鼻則孝が死んだら終わり。何年から何年までと区切られますよね。そうやって歴史に足あとを残すことのほうが、自分が求めている生き方に近いなと思うようになったんです。

清川:私はアーティストから始めたわけですけど、作品を見た人が、それをこういうところで使いたいと言ってくれたことで、デザイナーの仕事になっていきました。さらに、ものをつくるだけじゃなく、世界観そのものを表現してほしいと言われて、アートディレクターの仕事になっていったわけですが…、そういう変化が起こったそのときは混乱していましたね。だから、最初は自分の中では、それぞれを分けて活動していたんです。アーティストの作品とデザイナーの作品は違うって。
でも、分けなくてもいいんじゃないか、と最近は思うようになってきています。手を動かしてつくったものはもちろん作品だし、それこそ、いちばん最初は自分で自分を飾って表現していたわけですけど、それも作品だし、たくさんの人たちと一緒につくっていくものも作品だし…。全て自分が関わった作品だから、分ける必要はないんじゃないかと思うんですよ。
それに、いまは個人戦の時代じゃない気がしているんです。分かる人が分かればいい、ということではなくて、やっぱり伝わってこそだし、共有できてこそ、だと思う。何かしら、誰かに感じてもらうことが大切で、それが大きくなれば、みんなで時代をつくっていくようなことにもつながるのかなって。
舘鼻:僕らが生み出す作品は、コミュニケーションツールなんですよね。それを通して、何かを伝えたり、感じてもらったり、共有したりする。そのための装置を生み出している感覚が、僕の中にも非常に強くあります。だから単純に「靴をつくっています」ではなくて、その靴がどういう意味を持つのか、履いてくれた人が何を感じて、何を発信したくなるのか、ということまで考えます。いまこうやってしているおしゃべりも、もちろんコミュニケーションですが、作家にとっては、ものづくりはそれ以上にすごく有用なコミュニケーションの手段ですからね。
清川:本当にそう思います。私たちがしているのは、想像したことを形にして、見ている人にどこか余白を残すような仕事。どうして、ここにこれがあるんだろうとか、何でもいいんですけど、つくったものに触れた人が、余白の部分に何かを感じる。そういうことがすごく大事ですよね。

お客さまとの関係性が原動力
清川:ちなみに、舘鼻くんの原動力は何ですか?
舘鼻:お客さまとのサイクルですね。いまの僕の活動が靴から始まっているということもあるのですが、お客さまがいるということが当たり前なんですよ。だから、どういう作品にするのかも、注文されてから考えます。実際に面と向かって、お客さまと話し合うなかから作品を生み出しますから。
日本ではまだそこまで多くの人たちに履いていただいているわけじゃないんですけど、海外だとアメリカやイギリスなど、いろんなところで僕の靴を履いてくださっている人がいるんです。中には、僕がつくった靴しか履かないといってくださっている人も何人かいて、1回に30足とかオーダーされる。要するに、アーティストとパトロンの関係性です。
そういうお客さまが、わざわざ東京の青山にある僕のアトリエまで来てくれるわけですよ。そこでいろいろと話をして、どういう作品にするかを考えていく。で、出来上がったら、僕は必ず自分でお客さまのところまで届けにいくんです。まあ、そこで新しいオーダーをもらって帰ったりもするのですが(笑)、大体そういうサイクルなんです。でも、このサイクルは1人ではまわらなくて、自分とお客さまとのリレーションシップで成り立っています。その関係性が僕の原動力になっていると思いますね。

清川:私は普段の生活の中で、ニュースを見たりいろんなことをしているときに、必ず何か矛盾を感じるんですよ。自分と何かのギャップとか。それが作品になりやすいですね。
舘鼻:自分の感情は常に変化するわけですけど、それを形にしていくのが作家ですから。作品というツールを通じて、僕らはさまざまな想いを共有しようとしているのでしょうね。
挑戦することは僕らの仕事
舘鼻:あと、実は僕には前からすごく気になっていることがあるので、最後に聞きたいのですが、清川さんはその小さな体で、あれだけたくさんの仕事をしているわけですよね。どうやって時間をつくって仕事をしているのかなって、5年くらい前からずっと思っているんですよ(笑)。実際のところ、どういう毎日を送っているのですか?
清川:私、朝は5時に起きるんです。子どもが起きてしまうということもあるんですけど、もともと早起きなんですよ。起きてすぐ、子どものことをいろいろやって、それからメールをチェックしたりするのですが、いちばんアイデアが浮かんだり、ラフスケッチがはかどったりするのは、その後ですね。

舘鼻:それは何時から何時くらいの話ですか?
清川:自分が飽きるまでやるんですけど、大体、午前中です。アトリエに行くときもあるし、自宅のこともあるのですが、ただアイデアが浮かびやすいのは移動中なんです。そこでふわっといろいろ浮かんで、書き留めるのが次の日の朝、という感じですね。
舘鼻:アイデアが浮かんだときにメモを取るわけじゃないんですか?
清川:メモを取ってもなくしてしまうんですよ、私(笑)。でも、いいアイデアは必ず覚えていますから。
舘鼻:浮かんだアイデアは、割とすぐに作品化するのですか?
清川:そこはうまく言葉にできないのですが、頭の中に構造ができて、プロセスが決まって、ゴールが決まったら、作品にします。自分にしか分からない世界ですけど(笑)。ただ、その頭の中にあるものを周りに伝えるのが大変で…。
舘鼻:ああ、それは分かります。清川さんもそうだし、僕もそうなのですが、チームで動くじゃないですか。いろんな人に関わってもらうわけだから、ビジョンを共有しなくてはいけないのだけど、それを説明するのは大変ですよね。いつも葛藤の連続です。
清川:私もそうです。自分の中のゴールはここなのに、まだここにいる、どうしようって、いつも思っています。しかも、それが何個もあるし…。形にしていくのって、本当に大変ですよね。
舘鼻:とはいえ、こうして実際に会うと、清川さんはすごく優雅な時間を過ごしているように見えるんですよ。いつ忙しくしているのかなと不思議なんですけど、夜中まで仕事をしているのですか?
清川:夜中は必ず寝ています(笑)。5時に起きますから。だから、やっぱり朝ですね。朝の仕事のスピードは本当にすごくて、そこで全て終わらせるというくらいの速さでやっています。
あと、100点でなくてもいい、と思うようにはしていますね。放っておくと、120パーセントのクオリティーを追い求めてしまうほうなので、そのくらいの気持ちでいるのがちょうどいいんです。全てのことに飛び込むわけにはいかないので。さっきもお話ししたように、職人さんに「意味が分からない」と言われながらもアクリルに糸を閉じ込めたりして(笑)、毎回、新しいことに挑戦していますから。

舘鼻:挑戦することは、僕らの仕事ですからね。
清川:さっきも話したように、そこを理解してもらってチームでつくっていくのは本当に大変なんですけど、でも乗り越えて、作品を形にして、新しい世界が広がったときにはすごくうれしいんですよね。だからやめられないのかな、とも思いますけど。
舘鼻:よく分かります。僕のヒールレスシューズにしてもそうですが、実際に体験した感覚が予想していたものと違うと、みんな驚くわけです。そうやって新しい価値観を感じてもらえるような場を提供できたときは、本当にうれしいですよね。
(了)

清川あさみ
アーティスト
淡路島生まれ。2001年に初個展。03年より、写真に刺しゅうを施す手法を用いた作品制作を開始。水戸芸術館や東京・表参道ヒルズでの個展など、展覧会を全国で多数開催。 代表作に「美女採集」「Complex」シリーズ、絵本『銀河鉄道の夜』など。作家、谷川俊太郎氏との共作絵本『かみさまはいる いない?』が 2 年に一度のコングレス(児童書の世界大会)の日本代表に選ばれている。 「ベストデビュタント賞」受賞、VOCA展入賞、「VOGUE JAPAN Women of the Year」受賞、ASIAGRAPHアワード「創(つむぎ)賞」受賞。広告や空間など幅広いジャンルで国内外を問わず活躍している。現在は、福島ビエンナーレ「重陽の芸術祭」において、「智恵子抄」で著名な高村智恵子の生家でのインスタレーションも行っている。

舘鼻則孝
アーティスト
1985年、東京生まれ。歌舞伎町で銭湯「歌舞伎湯」を営む家系に生まれ、鎌倉で育つ。シュタイナー教育に基づく人形作家である母の影響で幼少期から手でものをつくることを覚える。東京藝術大学では絵画や彫刻を学び、後年は染織を専攻する。遊女に関する文化研究とともに日本の伝統的な染色技法である友禅染を用いた着物やげたの制作をする。近年はアーティストとして、国内外の展覧会へ参加する他、伝統工芸士との創作活動にも精力的に取り組んでいる。2016年3月には、カルティエ現代美術財団にて文楽の舞台を初監督し「TATEHANA BUNRAKU : The Love Suicides on the Bridge」を公演した。作品は、ニューヨークのメトロポリタン美術館やロンドンのビクトリア&アルバート博物館など、世界の著名な美術館に永久収蔵されている。
#Column
2017/08/15
2023/04/20
まわり、まわって。Vol.3 伊藤徹也氏
『カメラと旅の、まわり。』
2022/12/26
まわり、まわって。Vol.2樋口直哉氏
『料理と文章の、まわり。』
2021/03/11