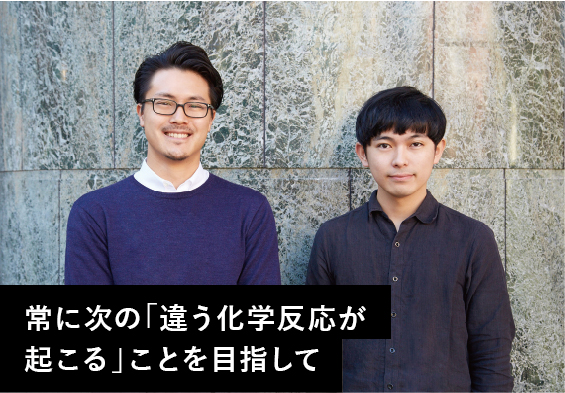2017/06/26
「ライブマーケティング」は、街全体が舞台!(後編)
- January / 31 / 2017
日本人は、複雑なものを計画的につくるのが得意
内藤:柴田さんは、店舗プロデュースだけではなく、渋谷のヒカリエやパレスホテルなども手掛けていますね。それなりの組織の集合体を考えるのに、いろいろつくり方の秘密があるんじゃないですか。
柴田:私も齋藤さんがおっしゃったような街づくりもとても興味があるんですけれど、私は物を考えるときに、人が起点なのです。人が好きだから常に人から始まっちゃって、「誰にどう思われたい街か」を起点につくるんです。
自分たちの持っている歴史だったり、自然などの財産だったり、人々の嗜好性だったりを考えて、まず「誰にどう思われたい街か」というのを考える。町内会や企業や個々の関係者の得意分野を思いやって整理しながら、協業的に物をつくっていく。そういう連携プレーができるところが、日本人の素晴らしい資質だと思う。
内藤:そうですね。例えばホテルがホテルだけの機能になっていて、レストランがレストランだけの機能になっているということはもうないんじゃないか思っています。われわれ3人はミラノ万博日本館にも一緒に取り組んで、齋藤さんには映像をやってもらって、柴田さんは飲食をやってもらった。世界から集まった多くの人に何を発信するかとなったとき、複雑に見せ方が組み合わさっていることこそが日本的なのかなと感じました。
今日話しているこの場所、サッポロ不動産の「GINZA PLACE」ビルの3階、「common ginza」も、柴田さんにカフェカンパニーの楠本修二郎さんを紹介してもらって立ち上げたんですけれど、超一等地の銀座4丁目交差点に位置し、まさに正面に和光の時計台が見えるベランダがあるなんて、こんな素晴らしいところは他にない。銀座の一等地というのは日本の一等地でもあるじゃないですか。だからカフェだけではなく、イベントでも活用できるように企画しました。海外から来た人たちにも、この場所で日本の文化を少しでも発信していけるといいなと思っています。


電通ライブが開発運営に携わっている「GINZA PLACE」3階「common ginza」内の「RAMO FRUTAS CAFE」。
カフェタイアップやイベント貸しもできます。
齋藤:せっかく世界の人が訪れる銀座のど真ん中ですから、マルチランゲージにいろんな文化の人たちが集まり交流できる場にできるといいですね!
柴田:私もそう思います。世界中の同じテーマに興味を持った人、好奇心のある人が、食べ物やイベントを通じて、実際の場所で理解を深め合うことはとても大事ですね。この場所で何か次の未来が開けるようなイベント、ここに行けば何か新しいヒントが得られるような場所になるといいですね。

「お・も・て・な・し」をオペレーションする
内藤:昔から「衣食住」といいますが、柴田さんは「食」のプロだけど実は「衣」も強くて、ファッションブランドを立ち上げているんですよね。
柴田:「BORDERS at BALCONY」というアパレルブランドを4年前ぐらいからやっています。
内藤:「住」でいうと、齋藤さんも多分柴田さんも、あとチームラボの猪子寿之さんとかも、みんなホテルのプロデュースをやりたいと言いますね。ホテルとか旅館とか。確かに日本型の旅館って「おもてなし」が全て詰まっているわけです。美しい食もあるし空間の変化もあるし、来てから帰るまでの間の一連のストーリーがあって、持って帰ってもらうお土産もある、そういうのが全て凝縮されていて日本的だからみんなやりたいのかな。
齋藤:確かに。
内藤:それで柴田さんと、「お・も・て・な・し」プロジェクトを立ち上げたんです。
柴田:「グレートおもてなしスタジオ!」
内藤:ウルトラだったり、グレートだったり(笑)。要は、われわれからすると、つくって納品して終わりの仕事が多かったんですね。柴田さんの場合は、お店の経営まで常に考えられているから、つくって終わりじゃなくて最後まで面倒見ますよというノウハウがあるので、柴田さんにご教示いただこうかと。
柴田:場所をつくるからには、そこで働く人の良い職場となり、来るお客さまにとっての居心地良い場所となり、それに対して投資をした経営側にとっても良いビジネスとなる、その「三方良し」の仕組みができない限り簡単に物をつくるなという考えが私にはあるんです。素晴らしいアイデアとか形を想像できる人に対し、私の方は「人の部分」に対して仕事するからこそ、齋藤さんみたいな一流の方とも一緒に協業ができる。
どういう場所で、来ていただいた方にこう思ってほしいから、こういう態度で振る舞いましょうという特徴づけですね。例えばオリンピックで外国人の方が日本にみえたときに、ボランティア全員が膝つき接客したら、侍の国・日本みたいな印象を持つでしょ。
何かしらの特徴をみんなでおそろいにすれば、感想を誘導できるじゃないですか。日本が一番美しく、豊かに映るような特徴をつくって、それを皆さんに教育をしたり覚えていただいて、楽しく実行していただいて、来ていただいた方に褒めていただいて、日本が狙うべき世界の感想を、きちんと持って帰っていただくというのをやりたい。
それは、商業施設だろうが街だろうがどこでもできること。日本交通の運転手さん教育をやらせていただいたときには、「ビジネスクラスのタクシー」というコンセプトの下、考え方や動き方を基準化して教育して、というのをやったんです。その企業のアイデンティティーを、人のおもてなしやオペレーションから感じていただくというようなことをしていきたい。
「運営の思想」を表現するための、プロトコルは誰がつくるのか?
齋藤:素晴らしいですね! 僕は最近デベロッパーとか街づくり系に関わって、よく冗談で言うんですが、うちが呼ばれるのはいつも「魔法使い枠」で呼ばれるんです(笑)。
柴田:あ、そうですよね。うらやましいなといつも思います(笑)。
齋藤:「ライゾマが来ると、ものすごいプロジェクションマッピングができる」と思われるのはありがたいのですが(笑)。でも実は、僕がいつも一番最初に提案するのは、運営の話なんですよ。
柴田:へえー。想像もつかないですね。
齋藤:運営をどうしていくかを考えた後に、コンテンツの話をしましょうと。
内藤:それは素晴らしいですね。
齋藤:それをやらないと、本当に一過性のものになって、3カ月ぐらいやると飽きられるんですよ。ちゃんとした運営の母体と思想があれば、きちんと予算をつけて定期的にアップデートをしていくという話になるんですね。最終的に場所をつくるのは人なのですから。
あと、僕はよくプロトコルという話をするのですが、日本って「ガラパゴスの美学」があると思う。日本語は日本人しか話さないし、ガラケーとかもガラパゴスケータイから来ているわけじゃないですか。日本の中でしかない文化、あいさつの方法、しきたり、おもてなしの文化があります。
日本の国内で考えると、競合同士では共通言語を持たないですよね。今この銀座4丁目交差点でいろんな色のネオンが光っていますけれど、例えば「2020のオリンピック開幕日の午後6時に、みんな一斉に赤にしましょう」とする。そういうのは誰が号令をして、どういうシステムでそれを実現できるのかというのは誰も分からない。みんなそれを話しもしない。要はプロトコルってイヤホンジャックみたいなもので、共通言語で話ができる方法を持っていない。それをまずつくることがすごく大事かなと思っている。
個人個人、一企業一企業、さまざまな施設ごとではいろんなコンテンツを考えたり、企画を考えていると思うんですが、それが横でつながっていったときにどういう線になるのか、もしくは面になるのかというのが大事じゃないですか。柴田さんがさっきおっしゃっていたみたいに、皆さんが日本にいらしたときに、同じあいさつ、話し方、口調、合図、サインがあるとか。そういうプロトコルを決められるのは、多分今しかない。

柴田:そうですね。
齋藤:それをどんどん具体的に実行に移すべきですね。バブルのころの箱物の反省もあって、やっぱり人が中心だということになると、人と人の出会いには、俗に言うおもてなし、時間的なお付き合いの流れが絶対できるわけだから、基本的にオペレーション的な視点がないと絶対成立しないなと思う。そこをつくらないと結局は何も表現できない。
前に水口哲也さんが言っていた「ウォームテック」という言葉があって、要は温かさ、温度を持っているテクノロジー。僕がやっていることはすごくそれに近いなと思った。テクノロジーって、AIだ、ロボットだと、どうしても温度が低い感があるんですけれど、実はそこに温かさも持たせることができる。
いろんなものがハイテクになっても、一番素晴らしいセンサーを搭載しているのは人間で、しかも人間が話すときに違和感なく話せるのもやっぱり同じ人間。F1のチームでも、AIだ、通信速度だ何だと全部計算してやっていても、一番最後にハンドルを握っているのは人間ですね。全部パーフェクトに、0.001秒まで全部制御したら、多分面白くなくなる。
テクノロジーで全て制御するのではなくて、人間や街がつくるばらつきも、すき間も含めて見せてあげるというのが、一番これからやるべきこと、可能性があるところなのかなと思います。.001秒まで全部制御したら、多分面白くなくなる。
テクノロジーという道具を使って、人が「生きる」街をつくる
内藤:柴田さんは、教育プログラムをつくって自ら講師にもなるし、デジタルも活用して店舗数の多い企業に対して、おもてなしのプログラムをたくさんつくっているんですよね。

柴田:はい。今「エアカレッジ」という会社をつくって、スマホ内で社員とかスタッフの方が見る番組みたいなもの、経営者の考え方や会社のオペレーションのルールや知識を、いろんな切り口から取り出せる動画をつくっていて、忙しいですけれど楽しいんですよ。
内藤:齋藤さんの今年の目標は?
齋藤:街は最終的に人からできていると、よくいうじゃないですか。いい喫茶店が一つできたら、その街が全部楽しくなると、北山総研の北山孝雄さんが言っていた。それをさらに、どう助長するのかがテクノロジーという道具ですから。昔でいう拡声器とかメガホンと同じような働きをするだけなので。どういう道具を組み合わせていくと生きるかというのが、街に対しても人に対しても、スケールのギャップを埋めていくのに役立つ気がするんです。今年はそれを目標に実行していきます。
柴田:電通ライブが世の中にとって大事な会社になっていただいて、企業や自治体の思いを集約してくだされば、私たちのような小さいブティックカンパニーなど、実行班はいっぱいいますよ。ホテルもつくりたいですね!
内藤:ぜひ、街を舞台にいろいろ一緒にやっていきましょう。電通ライブ、頑張りますのでこれからもよろしくお願いします!

齋藤 精一
ライゾマティクス クリエーティブディレクター / テクニカルディレクター
1975年神奈川生まれ。建築デザインを米コロンビア大学建築学科(MSAAD)で学び、2000年からニューヨークで活動を開始。その後Arnell Groupでクリエーティブとして活動し、2003年の越後妻有アートトリエンナーレでアーティストに選出されたのをきっかけに帰国。
その後フリーランスのクリエーティブとして活躍後、2006年にライゾマティクスを設立。建築で培ったロジカルな思考を基に、アート・コマーシャルの領域で立体・インタラクティブの作品多数つくり続けている。2009~14年国内外の広告賞で多数受賞。現在、ライゾマティクス代表取締役、京都精華大学デザイン学科非常勤講師。
2013年D&AD Digital Design部門審査員、2014年カンヌライオンズBranded Content and Entertainment部門審査員。2015年ミラノ万博日本館シアターコンテンツディレクター、六本木アートナイト2015でメディアアートディレクター。グッドデザイン賞2015-2016審査員。

柴田 陽子
柴田陽子事務所 代表取締役
神奈川県生まれ。大学卒業後は、外食企業に入社し、新規業態開発を担当。
その後、化粧品会社での商品開発やサロン業態開発なども経験し、2004年「柴田陽子事務所」を設立。企業に対する戦略立案、業態・新事業プロデュース、商品開発、ブランディングを領域とするコンサルティング業務を請け負う。
2014年セブン&アイホールディングス「グランツリー武蔵小杉」総合プロデューサーを
務め、2015年東急電鉄「ログロード代官山」「渋谷ヒカリエ レストランフロア」のプロデュース、2015年ミラノ万博における日本館レストランプロデュース、パレスホテル東京「7料飲施設」、ローソン「Uchi café Sweets」、ルミネ、日本交通などのブランディングに携わる。
また、“「理念浸透型経営」と「プロフェッショナル育成」を実現するためのプログラム”として、さまざまな教育の仕組みの開発や導入も行っている。
また、都内で飲食店を直営店として経営するほか、「自分が本当に納得のできる、ものづくりがしたい」という思いから理想の洋服つくりを始め、2013年アパレルブランド「BORDERS at BALCONY」を立ち上げる。

内藤 純
株式会社電通 イベントスペース&デザイン局 局長
電通ライブ取締役副社長COO
1985年電通入社。
展示会、ショールーム、店舗開発、都市開発など、多くの実績を誇る。
2005年の愛・地球博トヨタグループ館の総合プロデューサー、2015年ミラノ万博日本館展示プロデューサーをはじめ、国際博覧会において数多くのパビリオンをプロデュース。
スペース、映像、グラフィック、プロダクトなど幅広い領域でのクリエーター人脈とプロダクションネットワークを有する。現在は電通ライブ所属。
#Column
2017/07/31
2023/08/30
あらゆる空間をメディアに変える
「UN-SCALABLE VISION」が開く、
ビジネスの新たな可能性
2017/12/20
スノーピークの「好きなことをやって、社会のためになる経営」(前編)
2017/07/26