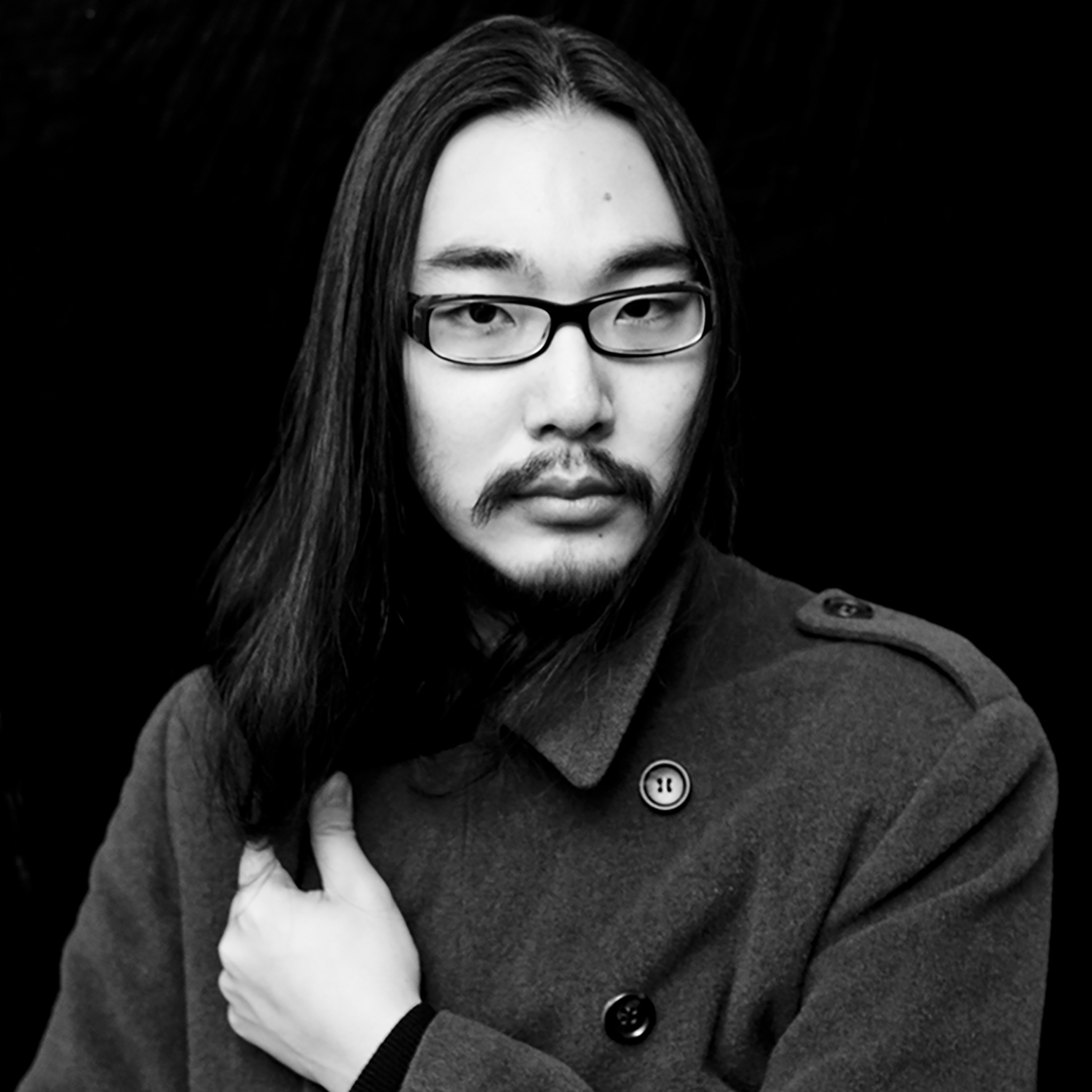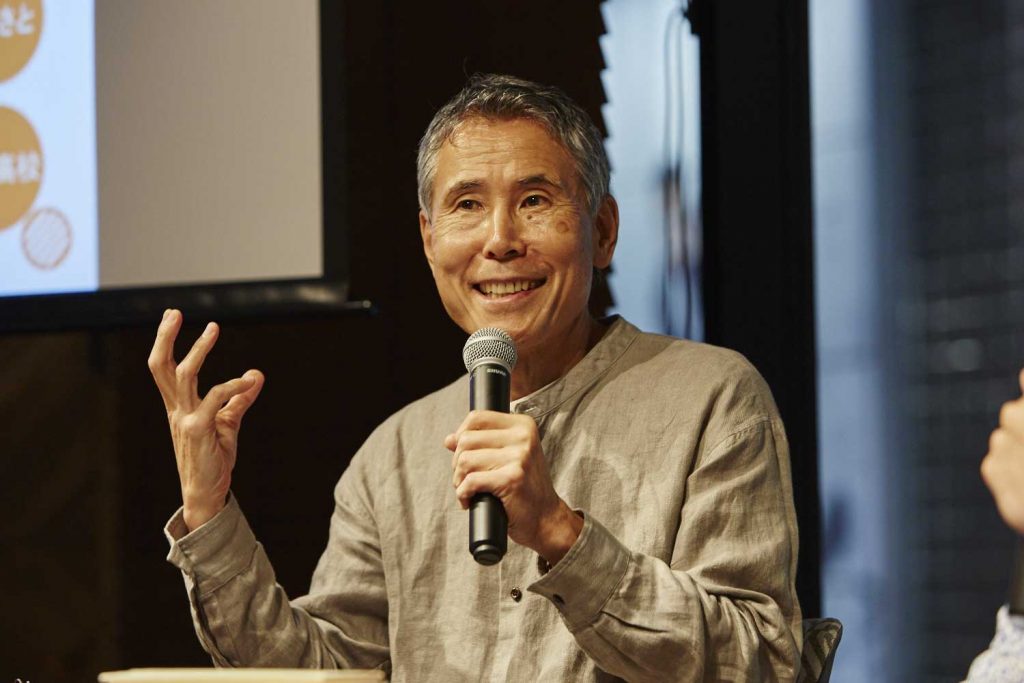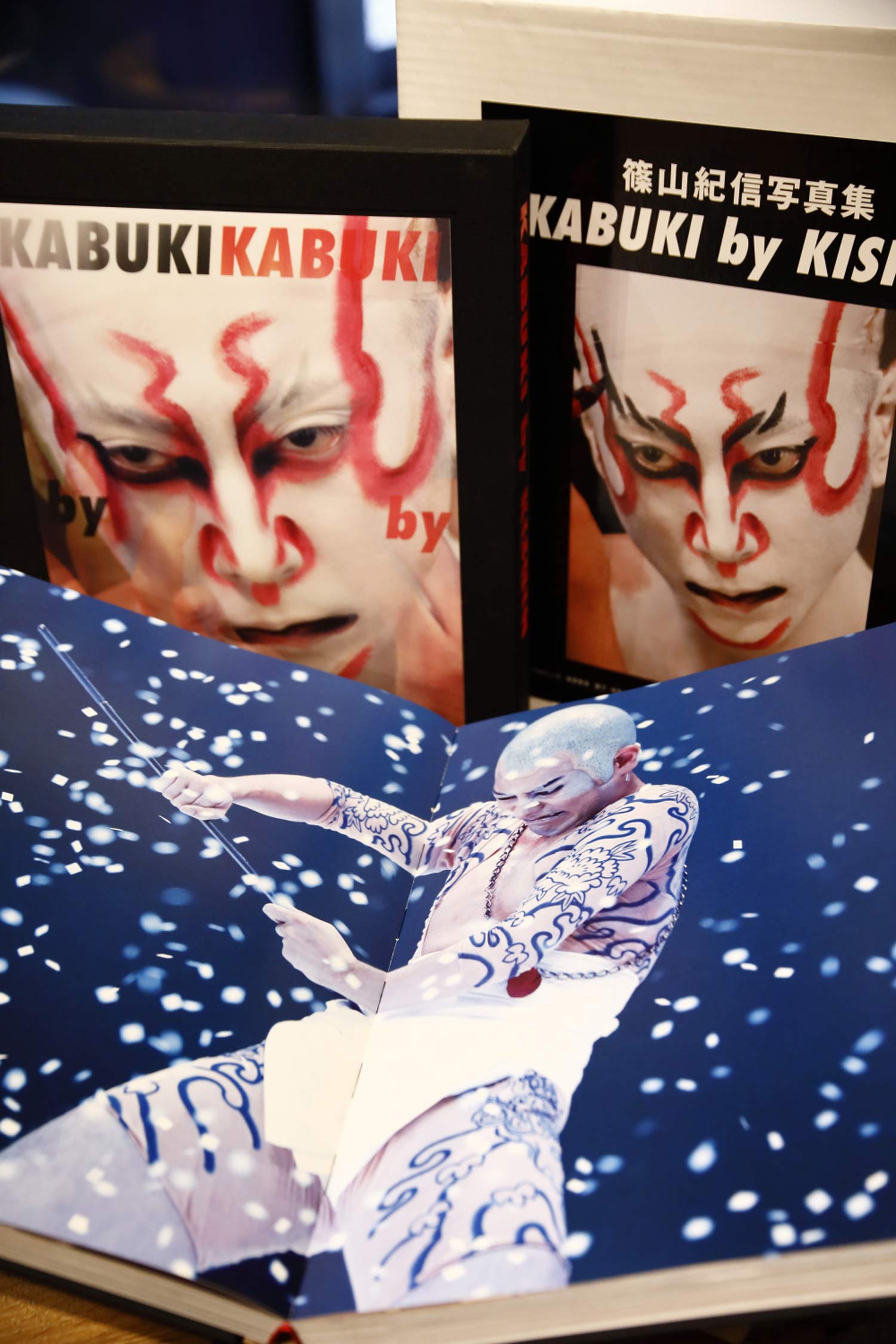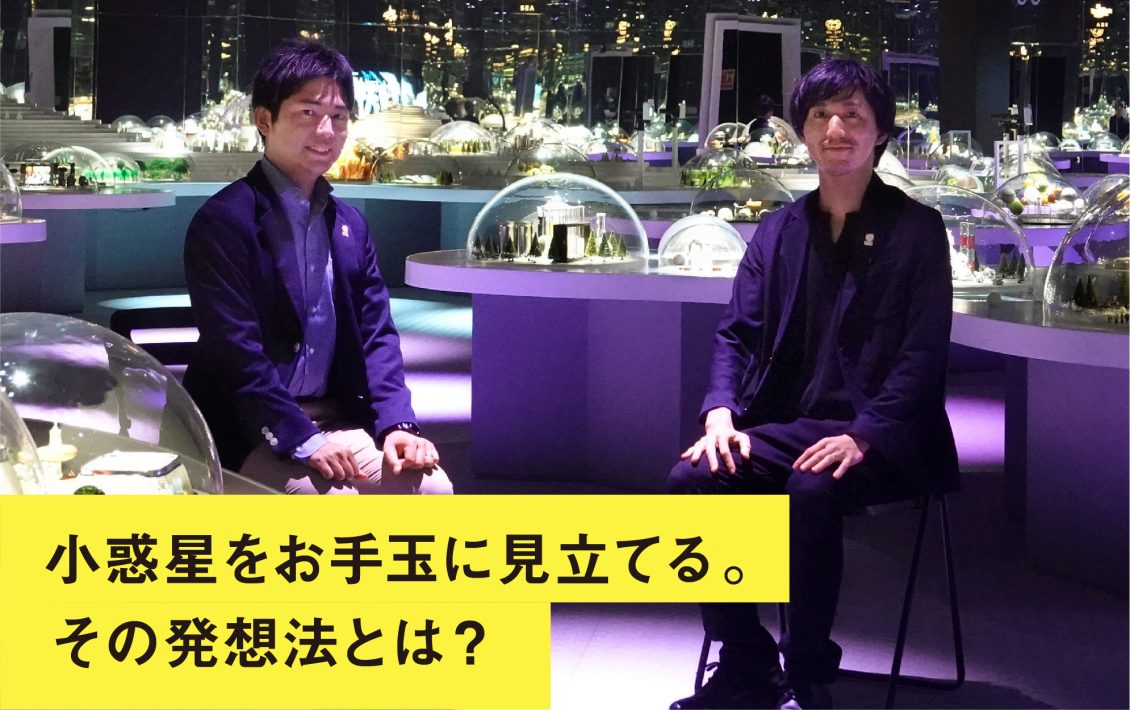2017/08/08
スノーピークの「好きなことをやって、社会のためになる経営」(後編)
- December / 20 / 2017
「地方の弱小企業」の「すごく高い目標」
国見:そのあたりのことを含めてスノーピークでは、企業のミッションとして「The Snow Peak Way」※というステートメントを書かれていますが、あれは非常にビジョナリーですよね。事業としての計画はもちろんあるのだけど、それ以上に明確なビジョンがあるからこそ、社員もついていくのだなと納得できます。
※「The Snow Peak Way」 https://www.snowpeak.co.jp/about/message/
山井:「The Snow Peak Way」を書いたのは、89年か、90年のことですが、当時は社員もまだ20人くらいでした。でも、キャンプには社会的なニーズがあることが分かってきていたし、いずれ日本に根付くという確信もありました。
そういう中で自分たちが社会に貢献できる企業になるためには、やっぱりベクトルを合わせたほうがいい。そんな思いから、僕も含めた当時のメンバーにまずは自分自身のミッションを書いてもらったんです。そして、それぞれの部署の中で書いたものを突き合わせてもらって、そこでのミッションを書いてもらい、全員分のミッションと、部署ごとのミッションを僕が預かって、自分の思いを加えたりして書き上げたのが、あのステートメントです。
「私達は自らもユーザーであるという立場で考え、お互いが感動できるモノやサービスを提供します」もそうですが、他にも「自然指向のライフスタイルを提案し実現するリーディングカンパニーをつくり上げよう」とか、「私達は、常に変化し、革新を起こし、時代の流れを変えていきます」とか、「私達は、私達に関わる全てのモノに良い影響を与えます」とか、新潟の燕三条にある弱小企業にしては、ものすごく高い目標を掲げていたと思いますよ。「私達スノーピークは、一人一人の個性が最も重要であると自覚し…… 」なんて、30年近くも前に、ダイバーシティを語ってもいますから(笑)。

国見:本田宗一郎さんが、創業して間もない頃に、従業員に向かって「これからは世界的な視野に立ってものを考えていこう」と話したら、吹き出した人がいた、というエピソードをどこかで読んだことがあるのですが、当時の日本の状況を考えると、普通の人が笑うのも分からなくはありません。でも、そのくらいの思いきった発言をする本田宗一郎という人がいたから、いまのホンダがあるのだと思うんです。それと同じで、「The Snow Peak Way」で高い目標を掲げたからこそ、いまのスノーピークの成長があるとも言えますよね。
山井:そうですね。ただ、「The Snow Peak Way」に関しては、僕がトップダウンで決めたわけじゃなくて、みんなが参加して決めたことなんです。それを掲げて30年近く、みんなで愚直にやってきた。そのことは大きかったなと思いますね。
「住まいや暮らしをつくるもの」としてのキャンプ
国見:いまはそこからさらに、いろんな事業を新たに立ち上げてもおられます。新規事業に取り組むときには、やっぱり「The Snow Peak Way」に立ち返られるのですか?
山井:スノーピークとしてやる事業はすべて、まず「The Snow Peak Way」に合致しているかどうかを考えます。例えば、アパレル事業にしても、アウトドアをテーマにしたブランドなんて、すでにたくさんあるわけですよ。でも、「ホームとテント」、つまりは「日常生活とキャンプシーン」をそのまま行き来できるものはまだないんです。東京で着てもかっこいいけど、キャンプシーンでもちゃんと機能する。そうであってこそ、スノーピークならではのアパレル事業ですよね。そういったコンセプトの部分は、特に大切にしています。
国見:山井さんの娘さんで、アパレル事業を立ち上げられた梨沙さんが、以前、「キャンプに行くときに、みんな登山用のアウターとか着ていくけど、本当はそんなのはいらないと思う。キャンプに行くのと、家にいるのと、同じ格好で大丈夫」とおっしゃっていたのがすごく印象的だったのですが、確かにそういうアパレルブランドはありませんし、そういう考え方はスノーピークらしくもありますよね。だいたいアウトドアの衣料って、自然に負けない、自然に打ち克つというスタンスでやっているところが多いと思うんです。でも、スノーピークはまったくそういうところがなくて、基本は共生ですから。

山井:少しだけ話は変わりますけど、アパレル事業といえば、表参道の直営店でうちの服を買ってくださっていた人が、1年くらいしてから初めて、「えっ、スノーピークって、キャンプもやってるの?」って気付いてキャンプを始めた、という話をこの間、聞いたんです。それってすごくいいことだなと思いましたね。ファッションの奥行きとしてキャンプがあるわけで……。だから、最近はそういう人向けにも、キャンプのイベントを組んだりしているんです。いまはユーザー全体の10パーセントくらいが、そっちから入ってこられています。
国見:他にも新たな試みとしては、マンション事業に関わったりもされています。
山井:そうですね。この春、東京の立川市に建った「パークホームズ立川」というマンションでは、三井不動産レジデンシャルさんとコラボレーションしました。マンションって、ご存じのように、上の階の部屋から売れていく傾向があるじゃないですか。1階の部屋は眺望のことや防犯上のことなんかもあって敬遠されることも多くて、少し値段を下げてやっと売れる、という感じです。でも、1階の部屋には専用庭がついていたりするんですよね。それを「野遊び」ができる場所だと捉えて、「半ソト空間」という名前をつけて、アウトドアライフを住居に取り込む提案をしたんです。しかも、強気に上層階と同じ価格で売り出した。そうしたら、なんと上の階の部屋よりも早く、1階が売り切れてしまったんですよ。
他にも、東京の中央区にある「パークタワー晴海」というタワーマンションでは、敷地内にキャンプサイトをプロデュースしたり、アウトドアの要素を取り入れたパーティールームをデザインしたりするだけじゃなく、モデルルームで専有部の内装にキャンプ用品やアウトドアグッズを取り入れた暮らしを提案したりもしています。いわば、マンションの毎日がキャンプ生活ということです。こういう取り組みをいくつかやってみると、僕らが思っている以上に、キャンプには住まいや暮らしをつくるものとしてのニーズがあるのだなと感じます。
国見:キャンプのニーズ、アウトドアのニーズは、オフィスにもあると思うんです。電通の僕らのチームも4年くらい前から、アウトドアオフィスをやっています。多いときだと週に1回。朝から夕方まで、ずっと外のテントの中で打ち合わせをするのですが、それだけで出てくるアイデアの質が全然違うんですよ。
山井:そうでしょ? 僕らも横浜市と一緒に実証実験をしたりしているのですが、午前中は普通にいつものオフィスで会議をやってもらって、午後はやっぱり外に出てスノーピークのテントの中で同じように会議をやってもらうんです。それで会議がどのくらい変わるのかを見るわけですが、質ももちろん変わりますけど、とにかく午前と午後では、働いている人たちの顔の表情が全然違ってしまうんですよ。
国見:それは本当によく分かります。アウトドアオフィスをやると、テントを畳んだ後に、仕事をすることが自分の人生の遊びのひとつになっているという実感が、ものすごく残るんです。だから、キャンプを休日だけのものとしているうちは、週に2日しか人間性の回復ができないのだけど、アウトドアオフィスを取り入れると、それが週7日にまで増える可能性があると思うんですよ。ただ、東京にはテントを立てる場所があまりないのが悩みどころで……。
山井:それでも、屋上でアウトドアオフィスをやったりする企業が増えてきていますよね。

好きなことをやって、社会のためになる
国見:話は変わりますけど、いまスノーピークはグランピング※にも力を入れていますよね。僕も今年の2月に、北海道の十勝でのグランピングに参加させていただきましたが、あれは非常に素晴らしい体験でした。
※グランピング……「魅力的」を意味する「グラマラス」と「キャンピング」からつくれらた造語で、優雅に自然を満喫できるキャンプのこと。
山井:恐らく日本で初めて行われた、本格的な本物のグランピングですね。
国見:でも、どうして冬の十勝なのですか?
山井:2月の十勝に来ませんか、気温はマイナス15度です、と話すと、「極寒」というイメージですよね。そこに魅力的な3日間が繰り広げられるなんて、誰も思わないじゃないですか。十勝の地元の人たちもそうなんですよ。大規模農場が多いので、冬は町全体がほぼ冬眠状態です。よそから人が来て、そんな場所で喜んで過ごすなんて、まったく思いもしない。そこに我々スノーピークが行って、グランピングというプラットフォームを提示して、犬ぞりとか、気球とか、もともとあったものも含めてコンテンツとしてパッケージして発信すると、どうなるか。それをやってみたかったんです。
食材も基本的にはオーガニックなものを使っているし、スノーピークはレストラン事業もやっていますから、そのレベルの料理を冬の十勝で食べてもらえる。そういう我々が持っているリソースを投入して、冬の十勝を豊かなものとして発信してみたわけです。実際に体験してみて、面白かったでしょう?
国見:面白かったし、自分の中での残存期間がすごく長いと感じました。日常に戻っても、ずっと体の中に体験が残っているんです。もちろん、キャンプに行っても近いことは起こるのだけど、グランピングはそれがずっと長いんです。
山井:十勝は本当に豊かな場所ですからね。でも、十勝と白馬は別格だとしても、自然は本来どこでもきれいなんです。東京の近くでも、筑波だってきれいだし。それに、どこの地方にも自然はあります。個性が違っているだけで、条件的にはそんなに変わらない。あとは、それを何とかしよう、生かそう、と思うかどうかなんです。
国見:実際に最近は、地方創生にもかなり力を入れておられますよね。地方のいろんな資産を使いながら、人間性が回復できる場を日本中につくっていこう、と。

山井:いまは全国で30カ所くらいの地方創生に関わっていますね。そもそも僕は、若い頃から、JC(日本青年会議所)やYEG(日本商工会議所青年部)に籍を置いたりして、地元の燕三条の街づくりには随分関わってきたんです。もちろんスノーピークも成長させたいと思っていましたけど、自分たちだけが良くなっても仕方がないじゃないですか。だから、燕三条の全ての産業が発展するように、できることをやろうと思ってやってきたんです。
そういう経験が根っこにあって、さらにスノーピークの活動をいろいろやっていく中で、キャンプをやるとまず個人の人間性が回復されて、次に家族の絆が深まって、コミュニティーができるということが分かってきた。地方創生は、その延長上にあるものだと思うんですよ。コミュニティーが集まったものが地方だと思うので。だから、僕の中では、キャンプから地方創生まで、全部がつながっているんです。
国見:昔、あるイベントでご一緒させていただいたときに、ふと思い立って、「山井さんの経営にロマンはどのくらいの割合を占めているんですか?」と質問したら、迷わず「9割」と答えられましたよね。「ロマンが9割の経営」って初めて聞きましたし、僕はいろんな社長とお仕事をさせていただいていますが、その中でも圧倒的に高い割合です。でも、そのロマンがあるからこそ、本当に大切なことに真っすぐに挑戦できるし、いまおっしゃったような大きな世界を描くこともできるのでしょうね。
山井:好きなことをやっているだけとも言えますけどね。スノーピークはもともと僕の父が創業した会社で、彼はロッククライミングが好きだった。僕はキャンプが好き。で、次の世代のうちの娘はアパレルが大好き。好きなものは違うんですけど、自分たちが好きな領域で仕事をして、それが社会のためになっている。同じことが、スノーピークに参加する誰にでも当てはまるといいなと思います。好きなことをやって、社会のためになるというオープンなプラットフォーム。スノーピークは、そんな会社でありたいですね。

(了)

山井太
株式会社スノーピーク 代表取締役社長
1959年、新潟県三条市生まれ。明治大学卒業後、外資系商社勤務を経て、86年に父親が創業したヤマコウ(現・スノーピーク)に入社。アウトドア用品の開発に着手し、オートキャンプのブランドを築く。96年から現職、社名をスノーピークに変更。毎年30~60泊をキャンプで過ごすアウトドア愛好家。徹底的にユーザーの立場に立った革新的なプロダクトやサービスを提供し続けている。株式会社スノーピークは14年12月、東証マザーズに上場。15年12月、東証1部に市場変更。

国見昭仁
株式会社電通 ビジネスデザインスクエア未来創造室 室長
1996年、都市銀行に入行。法人向け融資業務を担当した後、広告会社を経て、2004年に電通に入社。10年には、経営者と向き合って企業のあらゆる活動を“アイデア”で活性化させる「未来創造グループ」を立ち上げる。15年からエグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター。化粧品、家電、通信、アパレル、旅行、通販、外食、流通などさまざまな業界において、経営、人事、事業、チャネルなどの広範囲におけるビジネスデザインプロジェクトを多数手掛けている。
#Column
2022/06/28
2023/04/20
まわり、まわって。Vol.3 伊藤徹也氏
『カメラと旅の、まわり。』
2022/01/18
見立て作家・田中達也氏に聞く、ドバイ万博日本館へのアプローチ
2017/08/08
デジタルコミュニケーションで、人類を前進させる:杉山知之(後編)