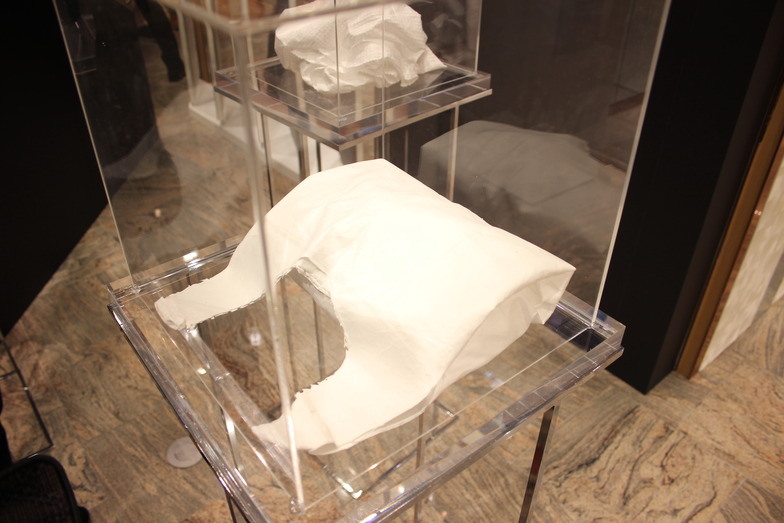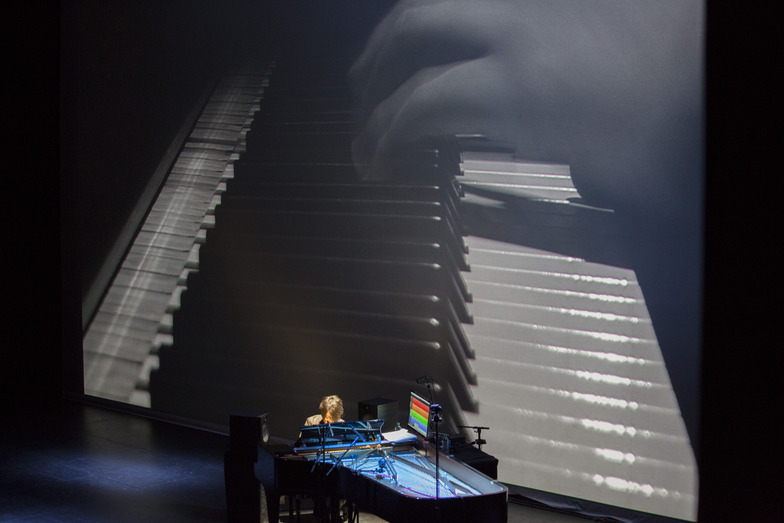2017/08/22
デジタルコミュニケーションで、人類を前進させる:杉山知之(前編)
- August / 08 / 2017
人類がデジタルでつながっているという、情報の「総量」が大事
金子:僕はデジタルハリウッド大学院を2期生として10年以上前に修了しました。通っていたころはプロダクションでプランナーをやっていましたが、修了してすぐ電通の社員になりました。デジタルハリウッドの教育は、10年前と何が大きく変わりましたか?
杉山:結局、人類がどのぐらいデジタルでつながっているかという総量が大事で、10年前はスマホもなかったでしょ。iPhoneが出たのが2007年なんです。
僕の感覚ではスマホは、パソコンで電話もできるという感じ。電話でメールもできるというのと、パソコンに電話機能がつくという感覚とでは、ビジネスの文脈が完全に変わった。だからこそスマホは、値段が高いにもかかわらず、先進国だけじゃなくて世界中に爆発的に広がっていったわけですね。全人類がネットにつながるという状況がとても加速しました。
若い人は、基本的に人類みんなつながっているという前提でビジネスを考えられる。アプリでも何でも、ネットの市場に出した瞬間に、世界中で売れる可能性がある。
僕が今相手にしている18歳くらいの学生は、物心ついたときにはスマホがあった。そうなるとSNSみたいなものが日常というか、ない世界は考えられないですよね。いつでも友達とつながっているし、つながり合っているぞというのをお互いに確認していないと関係が危ういという問題が起きるわけです。LINEで送ったのに返ってこないと「嫌なやつだ」とすぐなってしまったり。
金子:ネット内での生活のルールというか、お作法が変わってしまっている。むしろ、ネットのルールそのものが、リアルな友達関係の、リアルなお作法になってきたという感じがしますね。
「デジタルコンテンツづくりは全産業の発展に波及する」ことをたたき込む!
金子:学校に入ってきて最初に教えることに変化はありますか。

杉山:10年前はまだ、コンテンツ産業そのものを僕自身でプロモーションしているところがあって、まず「コンテンツ産業とは何ですか?」というところから始めました。放送、新聞、出版、音楽、ゲーム、モバイルと、みんな縦割りの業界になっていた。それがデジタルによって横につながってしまうので、昔の言葉ですけれどもワンソースマルチユースですね、一個原作があったら全てに展開できる。コンテンツ産業ではIP(知的財産)をいかに上手に使っていくか、映画化権もあれば、ゲーム化権、小説化権もあるわけですから。そんな始まりでした。
電通がやっている仕事でもありますけれど、コンテンツ産業はそういうダイナミックな産業なんだなということをまず世間にも学生にも、分かってもらう必要がありました。その中で、自分の得意をどこにつくるんだという教育が重要だと。
コンテンツ産業の持つ、要するに人の心を動かす技術というか、その総合プロデュースは、今や全産業界で必要。大学院生たちは次々と、ファッションテクノロジー分野、デジタルヘルス分野、または金融へ行ってフィンテックの分野とか、学んだ後の応用範囲をどんどん広げている現実があります。どの業界もビジュアライゼーションの知識や技術は核になっているわけです。そういうことを最初に徹底的にたたき込みます。
金子:本当に、新分野も含めて、全産業への影響になってきちゃいましたね。
杉山:18歳なので、ゲームが好きで来たとか、アニメが好きで来たという感じの学生も多いわけです。高校の先生や保護者から、「ゲームづくりをやりたいというけど、そんなことで食っていけるのか」とか言われながら入学して、でもここに来たら僕が、「なんなら全部の産業、どこにも行けるぜ」という話を最初するわけです。
最近、中央教育審議会から、専門職大学をつくりなさいという答申が出ましたが、日本の大学のカリキュラムが、ビジネス界に役に立たないようなことばかり教えているという判断が背景にあるように感じます。大学生でも職業観みたいなものを持てないまま卒業してフリーターになっちゃう子も実際多いので、専門職大学という形で、職業に通じる学士号を出そうということですよね。
デジタルハリウッド大学は、すでに専門職大学のようだと言われます。たしかにCGアニメーターやウェブデザイナーとして巣立つ学生も多いですが、僕の感覚でいえば普通の4年制大学の基礎教養科目みたいなものだと思っているのです。デジタルで自分が言いたいことを表現するのは、日本語の論文がきちんと書けるのと似たようなもの。22世紀に向けた教養学部と言ってしまってもいいぐらいの感覚です。たまたま強くそういう人材を求めているのが、現状ではゲーム産業であったり、ICTを基盤としている産業だというだけの話です。
杉山:入学して最初に、実習でデジタルツールの使い方をバババッと覚えて、何かつくろうというときに初めて、「物語を語らなきゃいけない」という問題にぶつかる。そのときに18歳の子の頭の中に、どれほどの数の物語があるかというと引き出しがない。この引き出しって何だろう、それが教養というものだよ、ということを理解してもらって、2年生以降には宗教、哲学、歴史などの教養科目をたくさん置いています。
例えば日本の近代史に詳しい先生であれば、一番面白いところだけ8回やってくださいと。それで面白いと思えば、今はネットに行けばいくらでも学べるし、自分で吸収できる。
金子:アクティブラーニング手法で、さらに火をつけるんですね。
杉山:デジタルハリウッドはデジタルツールのオンライン教育を10年以上やっているので、教材がかなり充実しているんですよ。例えばフォトショップを習いますとか、イラストレーターを習います的なやつですね。それは全部オンラインの教材として基礎から応用までそろえているので、それを院生と大学生には全て無料で開放しました。
金子:僕のころはなかった!
杉山:すみません(笑)。だから、先生が言ったことが分からなければ、家へ戻って、全部それを見直すとか、やる気がある子は2週間で全部やっちゃうとか。「フリップラーニング」(反転学習)ですね。家で勉強して、学校は議論の場にしたい。学校は、リアルな場所に通う意味を持たせなければならないのです。
論理的思考を構築できれば、起業家は目指せる
金子:最近は「G’s ACADEMY」(※)でプログラミング教育を始めてみたり、デジタルハリウッドの変化のキャッチアップへの源泉は何なんでしょうか。
※G’s ACADEMY:「セカイを変えるGEEKになろう。」をコンセプトに、デジタルハリウッドが2015年に創設した、エンジニアを育成するためのプログラミング専門のスクール。
杉山:僕たちの学校というのは、卒業したんだけど関係が切れない。むしろその境をうやむやにしているんです。卒業しても関わりたければ、何にでも関われる。
金子:確かに僕も、関係がうやむやです(笑)。
杉山:この人は何の立場でここに出入りしているのかなとあまり問わない。何年か前に修了した人らしいよ、ぐらいで大丈夫(笑)。そうすると入りやすいから、「今こんなことをやっています」と教えてくれたり「こんなことを一緒にやりませんか」と言ってくれる。「僕、アイデアがあるけど場所がないので、場所を貸してくれませんか」と言ってくる人もいます(笑)。
とにかく出入りしやすくしておくというのが、秘訣のような気がしますね。トレンディーな話題の研究会、外のいろんな企業の方が普通に出入りする場です。そういうワイガヤの状態から、いろんな人が知り合って、スタートアップのヒントにどんどんなっていく。
金子:その関係で出資を受けたり、資金調達が成り立っちゃうような事業化を考えている学生もいるわけですね。
杉山:そうですね。いわゆるインキュベーションとか、ファンドの事業をやっていらっしゃる会社がたくさんありますよね。そういう方がここに来てくれるので、教わるだけじゃなくて会社をつくるのも手伝ってくれるし、何なら資本金を入れてくれる人まで現れると思ったら、当然ながら活気づきますよね。シードアクセラレーションというのかな。
金子:ベースとして在校生や卒業生の多くが「起業しよう」という目標を持つように、教育として何をたたき込んでいるんですか。今、企業で人を育てる立場の人は、ぜひともアントレプレナーシップを持っていてほしいと願いながら人を育てていると思います。
杉山:そこを分かってもらいたいので、半年しかうちで学ばない人にも、僕が必ず直接授業をやっているんです。「デジタルコミュニケーション概論」という4時間の授業があって、いかにデジタルコミュニケーションによって全産業が革新するかという話をしているんですね。もちろん事例も見せながら。出席できなかった人も、必ずビデオで見なきゃいけないことになっています。

金子:僕も杉山学長のお話を聞きました。また必修科目の事業家の先生方が、各分野で濃いんですよね。「やばいぞ、これは」と何か電気のようなものが走って(笑)、あとは必死で勉強するみたいな(笑)。
杉山:僕は少しは研究者なので、単純な未来予測は結構できるわけです。いつかはこうなるだろう的な話ですが。でも学校は、「いつそれを教えるべきか」という問題もあるんですよ。あまり先過ぎると、教える人もいなければ、教えたところでどこにも理解されなくて就職できない。ちょうどいい頃合いというのがあると思ってます。

杉山 知之
デジタルハリウッド大学 学長/工学博士
1954年東京都生まれ。87年からMITメディアラボ客員研究員として3年間活動。90年国際メディア研究財団・主任研究員、93年 日本大学短期大学部専任講師を経て、94年10月 デジタルハリウッド設立。2004年日本初の株式会社立「デジタルハリウッド大学院」を開学。翌年、「デジタルハリウッド大学」を開学し、現在、学長を務めている。 2011年9月、上海音楽学院(中国)との合作学部「デジタルメディア芸術学院」を設立、同学院の学院長に就任。福岡コンテンツ産業振興会議会長、内閣官房知的財産戦略本部コンテンツ強化専門調査会委員を務め、また「新日本様式」協議会、CG-ARTS協会、デジタルコンテンツ協会など多くの委員を歴任。99年度デジタルメディア協会AMDアワード・功労賞受賞。 著書に「クール・ジャパン 世界が買いたがる日本」(祥伝社)、「クリエイター・スピリットとは何か?」(ちくまプリマー新書)他。

金子 正明
株式会社電通 イベント&スペース・デザイン局(2016年当時)
デジタルハリウッド大学大学院修了。2006年6月電通入社。新聞局で新領域案件に従事。 プロモーション事業局で人材育成を経験。イベント&スペース・デザイン局でエクスペリエンス・テクノロジー部のソリューション検討メンバー。
#Column
2017/11/01
「アーティスト」と「アートディレクター」の境目はどこにあるのか(前編)
2017/08/08
2017/08/15
2023/07/04
SCALE OUR FUTURE vol.2
『サステナビリティに配慮したイベントとは? ガイドラインを軸に考えるこれからのイベント制作』